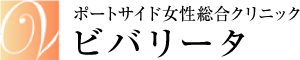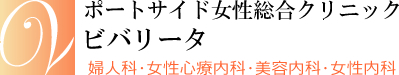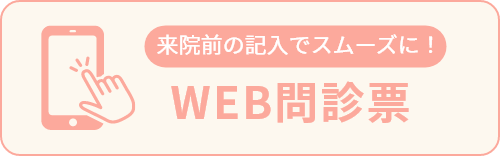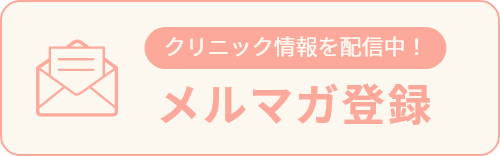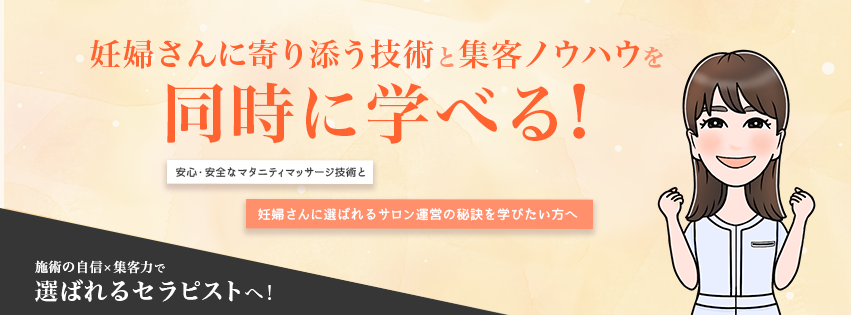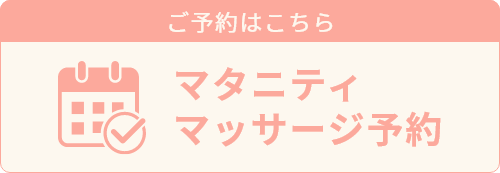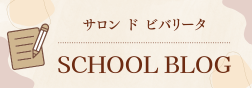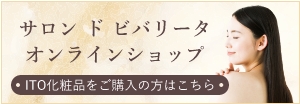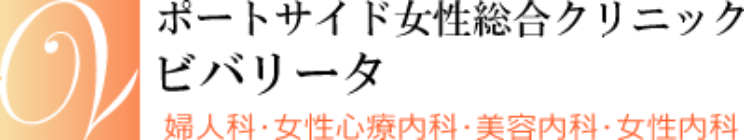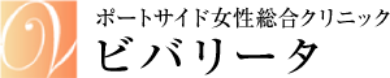女性検診
子宮頸がん検診の受診率
女性の癌発症率を見ると、20代では圧倒的に子宮頸癌が多くて、30代でもトップは子宮頸癌。30代になると乳癌が増えてはきますが、それでも子宮頸癌の半分くらいです。にもかかわらず、乳癌検診はピンクリボンキャンペーンなどでかなり大々的にアピールされていますが、子宮頸癌検診に関する情報はまだあまり広まっていません。
セックスの経験があれば、10代であっても1年に1回は子宮頸癌検診が必要であるということも、定期検診によって早期発見できれば子宮を残したままでほぼ100%の完治が期待できることも、ワクチンとコンドームによって予防できる癌であることも、ほとんど何も知らない人のほうが多いんですよね。
これが、日本女性の癌検診受診率が低い原因のひとつであることは確かです。若い人ほど検診を受けておらず、また妊娠・出産する年齢も上がってきているので婦人科に行く機会もありません。
「知らなかった」では済まされないことですが、実際はまだまだ必要な情報は伝わってないんですよね。
イギリスでは、25~64歳の女性が3年に1回(50歳以上は5年に1回)、全額公費で子宮頸癌の検診を受けられるようになっているそうです。そして、検診受診率は約80%・・・日本の15%とは大きく異なります。
また、HPV検査を併用することで、より検診の精度を上げているそうです。HPVワクチンは12~13歳で国の公費負担で実施されており、12~13歳で接種できなかった人も18歳までに再度受ける機会が設けられています。
ちなみに、HPVワクチンは世界105カ国で承認されており、先進国の中で承認されていないのは日本と北朝鮮と中国くらいでした。それが、昨年やっと承認されて、年末から接種が可能になりました。
オーストラリア・ノルウェー・ドイツなどでは、12~13歳の女性に国が全額公費で接種しています。ちょうど、昔の風疹の予防接種のような感じです。アメリカ・イギリス・フランスといった国々でも、大体11~14歳で接種するようになっています。
オーストラリアやニュージーランドやオランダでは、男性へのHPVワクチン接種も認められています。ワクチンそのものが非常に高いので、子宮頸癌になる側、つまり女性が優先的に接種の対象にはなるんですが、本当は女性にHPVを感染させるのは男性なわけですから、男女ともに予防接種した方がいいんですよね。
日本では、まだHPVワクチンを公費負担で行っている自治体はわずかで、接種にかかる費用約5万円は自己負担になります。本当は、中学入学時くらいに学校で集団接種した方が予防効果が期待できます。
HPVは性感染症なわけですから、性行動が始まる前に、女性全員に取りこぼしなく接種できることが大事なんです。
イギリスでは、中学生や高校生の頃からきちんと子宮頸がん予防や避妊に関する教育を受け、テレビのコマーシャルなどでも啓発されており、大学生になったら検診を受けるようにハガキが来るんだそうです。
10代の頃から「セックスの経験があれば子宮頸癌になる危険性がある。年に1回は子宮癌検診を受けること」ということをしっかりと刷り込まれているので、検診を受けるのが当たり前という意識が大人になる前に育っているんですね。
この辺りが、日本と海外の検診受診率の違いを生んでいるのではないでしょうか。日本では、ティーンを指導すべき立場の親や教師だって、子宮癌検診も乳癌検診も受けていなかったりしますからね。
病院は病気になった時に駆け込むもの、という認識を持っている人が多いのは、国がそういった教育をしてしまい、国民皆保険制度によって、「病気になっても安く治してもらえるんだから」というある意味健康意識の低い状態を育ててしまったからではないかと感じています。
これから日本の若い女性が子宮頸癌で子宮を失っていかないようにするためには、やはり検診の必要性を伝えていくしかないのですよね。私も、高校生に性教育に行くたびに「10代でも子宮頸癌検診が必要なんですよ」ということを呼びかけていっています。
検診を受けない最大の理由は「めんどくさい」なんだそうです。
自分だけは癌にならない、と思っている人に癌検診を受けてもらうための1つの動機付けとして、HPV検査は有効かもしれないなと思いました。癌になるかもしれないウイルスに感染していると分かれば、少しは真剣に検診を受けようって思ってはもらえないかしら。
がん検診の結果・新分類=ベセスダシステム
子宮頸がんの検査結果は、これまでクラス1~5の5段階で表現されていました。
この「クラス分類」は、結果をお伝えするのには分かりやすくて便利なのですが、微妙な異常を分類し切れなかったり「見落とし」につながることもあって、国際分類である「ベセスダシステム」に基づいた分類に変更することが推奨されるようになってきたんです。
ベセスダシステムに基づいた分類は次のような分け方になっています。
NILM(クラス1・2)=正常な細胞のみ
ASC-US(クラス2・3a)=異形成と言い切れないけれど細胞に変化がある
ASC-H(クラス3a・3b)=高度な細胞異型の可能性があるが確定できない
LSIL(クラス3a)=HPV感染や軽度異形成と考えられる
HSIL(クラス3a・3b・4)=中等度異形成・高度異形成・上皮内癌と考えられる
SCC(クラス4・5)=明らかな扁平上皮癌と考えられる
クラス分類より少し複雑で分かりにくいですよね?
以前の分類と何が異なるのかというと、ひとつは「HPV感染の有無」を重視していることです。明らかにHPV感染があると考えられる場合は、精密検査が必要なレベルに分類されることになります。もうひとつは、異形成のレベルを「軽度」と「中等度と高度」という2分類にまとめたことです。
それぞれの結果だった場合に、それをどのように扱うのかということになりますが、これは以前より単純になりました。
NILM→1年ごとの定期検診を続ける
ASC-US→HPV検査をして「陰性」なら1年ごとの定期検診・「陽性」ならコルポ診
ASC-H・LSIL→コルポ診
HSIL→コルポ診+頚管内組織検査又は円錐切除
SCC→円錐切除又はそれ以上の手術
つまり、明らかに正常な場合と明らかに癌であるという場合を除いて、ほとんどがコルポ診という精密検査が必要になるということです。
コルポ診というのは、子宮の出口を拡大して観察する方法です。通常はコルポ診で最も病変が強いと思われる部分を一部かじりとって「組織診断」を行います。それによって、単なる炎症なのか異形成なのか、異形成なら軽度~高度のどのレベルなのかといったことをより詳しく見ていきます。
また、最近はHPVハイリスクタイプの検査を今までの子宮頸がん検診と一緒に行うことで、より精度を上げることができるということも言われてきています。子宮がん検診とHPV検査のいずれも「陰性」であった場合は、ほぼ100%現時点で軽度異形成以上の病気はないと判断できるんですね。そのため、アメリカでは療法の検査が「陰性」であれば、次の検診は3年後としています。
日本でも、自治体の検診はほとんどの地域が2年に1回になっていますから、見落としなく効率よく検診をしていくには、HPV検査を併用した方が「異常なし」の方の検診頻度を少なくしていくことができるのではないかと思われます。