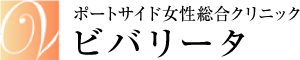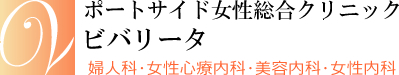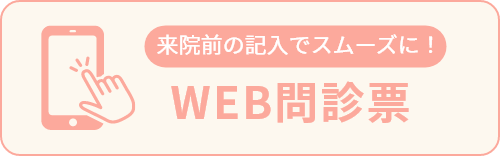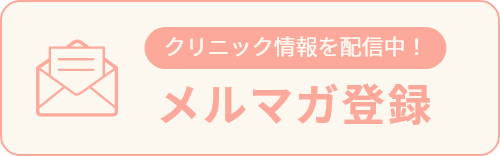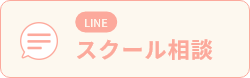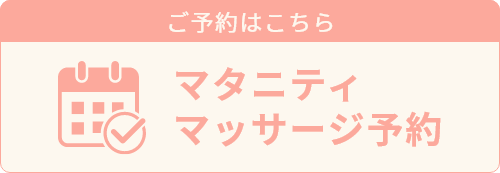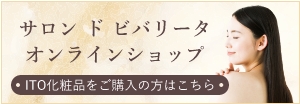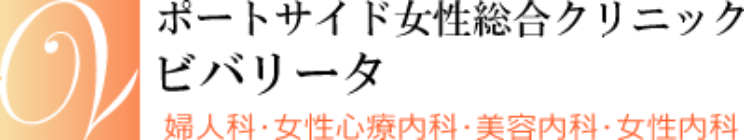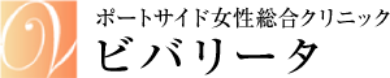子宮頸がん検診
クラス3aといわれたら【横浜駅近く女医の婦人科】
子宮頚がん検診で「クラス3a」の意味は?(横浜 婦人科 おすすめ 年末年始)
子宮頚がん検診で異常所見が出たときの対処法については、担当の医師によって方針が異なったり、ご本人の希望やライフプランに応じて対応が変わってくるので、「これが正しい」ということはお伝えしにくいのですが。
一番ご質問を頂くことが多いのが「クラス3aでちょっと異常だけど様子を見ましょうといわれたんですが・・・」というものなんですよね。異常所見が出たときの扱いについて少し詳しくご説明したいと思います。
「クラス3a」は「異常があるかもしれない」というレベルなので、自覚症状はほぼありません。一度異常な細胞が出ても、自然に治ることの方が多いので、ほとんどの場合は定期的な検査を繰り返して、様子を見ていきます。
実際、「クラス3a」が出ても、自然に治るケースがほとんどなのです。
旧式の子宮頸がん検診結果が「クラス分類」(横浜駅 評判いい 近くの 婦人科 年末年始)
旧式の子宮頚癌検診の結果表記だと、クラス1~5の5段階で返ってきます。ちなみに、最近は「ベセスダシステム」という新しい表記方法に変わってきているので、クラス分類で表記されることは少なくなっています。
クラス1は、「正常な細胞だけです。何も心配ありません」という意味。今の段階で癌の心配は全くないということです。ただし、この結果の有効期限は1年と思って下さいね。1年に1回の検診を受けていれば大丈夫です。
クラス2は、「癌の心配は無いけれど、何らかの良性変化があります」という意味。良性変化は主に、炎症による変化か年齢的な変化ですね。おりものの中の雑菌にかぶれたりすると、炎症による変化がみられたりします。クラスが1から2になったからといって、さらに上のクラスに進んで行っているというわけではありませんからご安心を。炎症が治まれば、またクラス1に戻ることもありますし、クラス2のままのこともありますから、両者の違いはあまり気にする必要はないんですよ。この段階も、1年に1回の検診を受けていれば大丈夫です。
クラス3はちょっと飛ばして、先にクラス4と5について。これは「癌を強く疑う細胞がみられます。直ちに詳しい検査及び治療を受けてください」という意味。この段階で何もせずに様子を見ることは、まずないと思っていいでしょう。どんな検査や治療をするかは、ケースバイケースですから、その先の方針については省略しますね。
子宮頚がん「クラス3」はグレーゾーン(横浜市 おすすめ 婦人科 女医 年末年始)
さて、一番扱いに困るのがクラス3が出た時です。クラス3はいわゆる「グレーゾーン」で、「癌とは言えないけれど、細胞の形が変化しつつあります」という意味。細胞の形の変化の強さによって、クラス3aとクラス3bに細かく分かれます。
物凄く大雑把に言うと、クラス3aは「細胞の顔つきが少しだけ変化してきています」という意味で、医学的に言ったら「軽度異形成」の状態。クラス3bは「細胞の顔つきがかなり変化してきています」という意味で、この段階を「高度異形成」と呼びます。
高度異形成は、癌の一歩手前の状態で、何もせずにほっておくと数年のうちに癌化する確率が高いといわれています。また、細胞診では「高度異形成」でもより詳しく調べてみると「上皮内癌」という癌のごくごく初期の段階が混ざっていることもあるので、クラス3bが出たら、普通はさらに詳しい検査をして治療の方針を決めていきます。
この段階できちんと治療すれば、「子宮腟部円錐切除術」という子宮の出口のホンの一部を切除する手術でほぼ完治できます。つまり、子宮を残したままで完治が望めるというわけです。定期的な子宮癌検診は、この段階で早期発見し、妊よう性(妊娠できる状態)を保ったまま完治を目指す事を目的としているんです。
「クラス3a」は自然に治る?(女医だけ 婦人科 おすすめ 年末年始)
では、クラス3aつまり軽度異形成の場合はどうするのでしょうか。実は、クラス3aという結果の中には、子宮の出口に強い炎症が起こっているために細胞にも強い変化が見られていますよ、というケースも含まれています。例えば、先日実際にあった症例ですが、クラミジア感染による炎症が強い時に癌検診をしたらクラス3aが出て、クラミジアの治療をした後にもう一度癌検診をしたらクラス2になっていたんですね。
クラス3bはほっておくと自然に正常な細胞に戻っていく事は少なく、癌へと進行していく確率の方が高いのですが、クラス3aはこのような一時的な炎症による変化も含まれているので、7~9割の人は自然にクラス1や2に戻っていくんです。だから、初めてクラス3aが出たらたいてい「3ヵ月後にもう一度検査を受けてください」と言われると思います。これは、3ヶ月では軽度異形成の状態から癌になることは理論上考えにくいからです。
3ヶ月で炎症が治まって自然にクラス1や2に戻っていれば、それ以上詳しい検査をする必要はありません。半年後にもう一度検査をして、2回連続でクラス1や2が出れば後は普通の人と同じように1年毎の検診を受けてください、となるわけです。
逆に、もし連続でクラス3aが出たら、その一部にクラス3bつまり高度異形成が混ざっていないかを確かめるために「組織診」と言って、子宮の出口の一部をかじりとってよりたくさんの細胞を調べる検査をします。この検査でも「軽度異形成」と言う結果が出たら、自然に正常に戻る可能性のほうが高いわけですから、「また3ヶ月ごとに癌検診を受けましょう」と言う事になります。大体、7~9割が2年以内に正常に戻るというデータがあります。だから、「いつまで検査を受け続けるの・・・」なんて辟易せずに、きちんとフォローアップを受けるようにしてくださいね。
7~9割という事は、残りの1~3割はどうなるの?と思われる方も多いでしょう。残念ながら、軽度異形成の状態から徐々に高度異形成を経て癌へと進んでいくケースもあるんですね。ただし、癌になるまでの細胞の変化は、普通何年もかけて進行していきます。正常な細胞が癌になるまでに3~7年かかるといわれていますから、3ヶ月毎や半年毎にきちんとフォローアップの検査を受けていれば、癌になりきる前に発見する事ができるんですよ。
「高度異形成になるまで検査を受け続けて、そうなったとこで治療すればいいって事?」
その通りです。徐々に進んでいく細胞の変化を食い止めたり、予防したりすることは、残念ながら今の西洋医学の分野では行われていません。早期発見を心がけ、見つかったところで治療をする事しかできないんです。
もし私が、今、クラス3aですよと言われたら、3ヶ月に1回だけその事を思い出してきっちり検診を受け、それ以外の日は子宮の事なんてどっかに忘れて毎日を楽しむと思います。毎日しっかり笑ってしっかり楽しんで、免疫力を上げる事が、病気を吹っ飛ばすにはとっても大事なんですよ。
ここに書いている内容は、日本産婦人科学会が子宮がん検診の結果の表記方法を変更する前の「クラス分類」の解釈です。
現在は「ベセスダ分類」という新しい表記方法に変わってきています。そのため、「クラス3a」の代わりに「ASC-US」または「LSIL」という記号が書いてあるか、両方が併記されているかもしれません。
「ASC-US」だった場合は、「クラスⅢa」でもそのまま放置するのではなく、「HPV検査」を追加します。
実は、がん検診の結果の表記が新しくなったために、結果の解釈やその後の対処法がまだ若干統一されていないところがあります。自分の検査結果や治療方針に少しでも不安や疑問があったら、まずは主治医にきちんと質問しましょうね。
ご予約はこちらから
日付:2026年1月27日 カテゴリー:女性検診,子宮頸がん検診
子宮頚がん検診(婦人科検診)でLSIL(エルシル)やHSIL(ハイシル)【横浜駅近くで評判の婦人科】
子宮頚がん検診(婦人科検診)の結果でLSILやHSILだと要注意?(横浜市 おすすめ 婦人科 土曜日午後)
子宮頸がんの検診結果は、以前の「クラス分類」から新しい「べセスダ分類」の表記に変更されてきている検診施設が多いようです。
各表記の意味はあまり詳しく解説されていないことが多く、検診の結果を受け取って慌ててお電話して来られる方も少なくありません。
婦人科検診で「LSIL」や「HSIL」だった場合、すぐに産婦人科を受診する必要があります。
結果の「ASC-US」についての解釈は、過去の記事「子宮頸がん検診でASC-USだった場合」をご参照ください。
結果が「LSIL」の場合、細胞を見る限りは「軽度異形成」を疑う変化がありますよ、ということを意味します。また、ASC-USよりもHPVへの感染を強く疑う所見が見られる場合も「LSIL」になります。
「異形成」というのは、正常な細胞とがん細胞の間のグレーゾーンの細胞を指すもので、細胞の変化の程度によって軽度→中等度→高度と徐々に進んでいきます。婦人科検査(細胞診)の結果が「LSIL」だった場合は、この「異形成」の中でも「軽度異形成」つまり、白に近いグレーの可能性が高いということを意味してます。ただし、細胞診はブラシなどでこすり取った表面の細胞のみを見ていますから、本当に「軽度」までの異常なのか、それ以上進んだ病変がないかを確認するために、より詳しい検査として「コルポスコピー検査」と「組織診」が必要になります。
コルポスコピー検査は痛い?(横浜駅 評判いい 近くの 婦人科 土曜日)
コルポスコピー検査は、子宮頸部(膣の方から見える部分)を拡大して、異形成を疑う変化がないかを目で見て確認する検査です。
組織診はコルポスコピーで覗いてみて、「ここが異常がありそうだ」と思われる部分を、少しまとまった組織としてかじり取る検査です。鳥のくちばしのような形をした検査用の器具で、子宮頸部の一部をパチンとかじり取ります。
コルポスコピー検査は、ただ拡大してみるだけなので痛みはありません。組織診は、取る瞬間に鈍い痛みを感じることがあります。もともと子宮頸部は知覚的に鈍い場所なので、それほど強い痛みはなく検査は無麻酔で行えます。
HSILは「がんの一歩手前」の場合も(横浜市 おすすめ 婦人科 女医)
がん検診の結果が「HSIL」の場合は、細胞の変化のレベルが「LSIL」よりも進んでおり、「中等度異形成」や「高度異形成」が疑われるということを意味します。この場合も、「LSIL」の時と同じように、まずはコルポスコピー検査と組織診を行います。
組織診断の結果が、「高度異形成」や「上皮内癌(がんの初期)」だった場合はその時点で治療、つまり手術が必要になります。高度異形成まで変化が進んでしまうと自然に正常化する可能性は低く、がんに進んでいくリスクが高いからです。
この段階で適切な方法で手術を受ければ、がんになってしまう前に「完治」することが期待できます。
組織診断の結果が「軽度異形成」や「中等度異形成」の場合は、基本的には定期的な細胞診を繰り返して、異常が進んでいかないかを注意してみていきます。
最近は、どのHPVの型に感染していると、異形成からがんに進むリスクが高いのかということまでわかってきたため、組織診が「軽度異形成」や「中等度異形成」だった場合は、HPVの型を調べる「タイピング検査」を追加する場合もあります。
感染しているウイルスの型が「がんに進む可能性が高いタイプ」なのか「それほど悪さはしにくいタイプ」なのかを調べることで、厳重注意が必要なのかそれほど心配しなくていいのかを区別することができるのです。
婦人科検診でLSILやHSILだったので精密検査をご希望という方は、お電話でご予約を承っております。
予約専用電話 045-440-5577
日付:2026年1月24日 カテゴリー:女性検診,子宮頸がん検診
子宮頸がん検診でASC-US(アスカス)だった場合【横浜で評判の婦人科】
がん検診の「ASC-US」ストレスでなる?がんの可能性は?(横浜市 評判いい 婦人科 土曜日)
子宮頸がん検診の結果の中で、一番混乱されるのがやはり「ASC-US」という結果だった時のようですね。ネットの知恵袋などで、「ASC-USと言われたら?」と質問してしまうケースも多いようです。
「ASC-US」はストレスで発生するのか?といった不安を抱える方もいらっしゃるかもしれませんが、「ASC-US」とストレスは直接的な関係はありません。
婦人科の検診で「異常です」と言われると、「ASC-US」だと癌なの?と不安になるかもしれませんが、「ASC-US」は「明らかに癌ですよ」という意味ではありません。
グレーゾーンなので、癌の確率が「ゼロ」とは言い切れませんが、どちらかというと「がんの手前」であることがほとんどです。
婦人科検診の「ASC-US」は、子宮頚部の細胞に「がんではないけれど完全に正常とも言えないグレーゾーンの変化」があるけれど、「もしかしたら一時的な変化かもしれません」という意味です。
健診で指摘される異常の中では比較的よくあるレベルの異常です。前回の検診では「異常なし」と言われていたのに、1年後に受けたら「ASC-US」だった、ということもあり得ます。
学会のガイドラインでは、検査結果が「ASC-US」だった場合は次のいずれかの対応をすることになっています。
1)半年後に子宮頸がん検査を再検査する
2)HPVハイリスクタイプの検査をする
3)コルポスコピー検査をする
「ASC-US」と言われたらまずHPV検査(横浜駅 近く おすすめ 婦人科)
このうち、推奨されているのは2)の、まずはHPV検査を行うという方法です。
HPVはハイリスクタイプに分類される「型」に感染すると、子宮頚部の細胞に変化を引き起こして、最終的にがん化させてしまう可能性があるウイルスです。
子宮頸がんワクチンで予防しているのは、このHPVへの感染です。全部で100種類以上の「型」があるウイルスですが、子宮頸がんのリスクになりうるのは、16型・18型が最も多く、その他31型・52型・58型など全部で13~15種類の型に限られます。
この、HPVのハイリスクタイプに感染しているかどうかを調べるのがHPV検査です。子宮頚部に付着しているおりものをぬぐい取る検査なので、ちょっとこするだけで完了します。
当院でも「ASC-US」だった方にはすぐにコルポスコピー検査は行わずHPV検査をするようにしています。当院で細胞診を行った方の場合は、HPV検査のために再度内診をしなくても、一度とった細胞でHPVの検査を追加できます。
いきなりコルポスコピー検査をしてもいいのですが、HPV陰性であれば行わなくていい検査なわけですから、無駄な検査をしないという意味でもHPV検査を行うのが効率的だと考えております。
また、組織診は痛みや出血を伴う検査ですので、本当に必要な方のみに行えるようにという意図もあります。
実際、ASC-USだったけれどHPVは陰性という方も2割くらいはいらっしゃいます。逆に言えば、ASC-USだとHPVも陽性なケースの方が多いわけです。
「ASC-US」だと癌の可能性はある?(横浜 婦人科 女医 おすすめ)
ASC-USでHPVも陽性だった場合に組織診を行うと、ほとんどは軽度異形成又は中等度異形成という結果が返ってきます。なので、「ASC-US」だと癌の確率が高い、というわけではありません。「ASC-US」だった人が「実は癌だった」という確率はを算出することは難しいのですが、当院で経験した「ASC-USで精密検査をしたら癌だった」というケースは今のところ2例です。
このように、ごくまれに、高度異形成や上皮内癌であるケースもありますので、ASC-USだから安心してよいというわけでもないのです。ただ、ASC-USで精密検査をしてみたら浸潤がんだったというケースは今まで出ておりません。
そういう意味では、ASC-USでがんの確率は非常に低いと言えます。
進んだ癌になりきる前に異常を見つけるためにも、こういった早い段階の異常をしっかり見分ける事が重要です。
HPVハイリスクタイプの検査は、子宮頸がん検査がASC-USだった方のみ保険で行えます。それ以外の方や、子宮頸がん検査と一緒に行う場合は自費になります。
この検査が「陽性」だった場合、数種類あるHPVハイリスクタイプのうち「どれかが陽性」という意味ですので、ワクチンの対象となる「16型・18型・31型・33型・45型・52型・58型」が陽性なのかそれ以外のタイプが陽性なのかは判別できません。
「何型が陽性なのか知りたい」という場合は、HPVタイピング検査を行うことでよりはっきり調べることが可能です。
HPVタイピング検査は、精密検査である組織診断で軽度異形成(CIN1)や中等度異形成(CIN2)と診断された場合にのみ、保険で検査が可能です。保険を使って検査をしても、自己負担額が約7000円と、ちょっと高額な検査になります。
ストレスでASC-USになる?(横浜市 おすすめ 婦人科 女医)
検診で異常を指摘されたからといって、全部ががんになってしまうものではありません。
必要な精密検査を受けて、どのように経過を見ていけばいいのか、しっかり主治医に確認しておくと安心です。
子宮頚部の細胞に変化が起きる原因の大部分は、HPVへの感染です。2番目に影響が大きいのはタバコです。
なので、子宮頚がんを予防したかったら、ワクチンでHPVへの感染を防ぎ、定期的に検診を受け、タバコを吸わないことです。
そして、上記以外の、子宮頚がんを予防する有効な方法はありません。何かを食べたり、運動したり、ストレスをなくしたりすることで、HPVへの感染を防ぐことができるわけではありません。
では、ストレスや寝不足が、細胞の変化と全く関係ないのか?と言いますと、多少影響する可能性があります。感染したHPVが活動してしまう要因の一つとして、自分自身の免疫力の低下が挙げられるからです。
「今、自分は、ストレスフルな生活をしている」と認識している時に、「ASC-US」という結果が出たのであれば、それは、「もうちょっと自分をいたわりましょう」というサインかもしれません。
「過去に異常を指摘されたことがあるけれどどうしたらいい?」「今回の検診でASC-USだったので心配」というご相談も承れますので、まずは気軽にご相談くださいませ。
ご予約はこちらから
日付:2026年1月20日 カテゴリー:女性検診,子宮頸がん検診
子宮頚がん検診でLSILだとがんの可能性は?【横浜で評判の婦人科】
「LSIL」と言われたら?(横浜市 婦人科 女医 おすすめ)
子宮頚がん検診を受けて「精密検査が必要です、医療機関を受診してください」という通知が来るのは次のいずれかの結果の場合です。
ASC-US
LSIL
ASC-H
HSIL
これらの記号は「ベセスダシステム」という、子宮頚がん検診の結果の表記方法で、それぞれのアルファベットが「細胞にどの程度変化があるか」を示しています。
ちなみに、「SCC」だと「明らかにがん細胞があります」という結果なので、「精密検査」ではなく治療のために大きな病院へ受診する必要性が出てきます。
通常、正常な細胞が「がん細胞」に置き換わるには、何年もかかります。なので、何も症状がなくて、定期的に検診を受けている人が、いきなり「SCC」の結果を受け取ることは非常にまれであると言えます。
「LSIL」はがんの可能性あり?(横浜駅 近く 評判いい 婦人科)
前述の4つの記号は、「がん細胞と正常な細胞の間」である「異形成」という状態を示しています。
検診で異常が出たら、「癌かもしれない」と不安になるかもしれませんが、異常が全て「がんですよ」という意味ではありません。
ASC-USとASC-Hは「異形成と思われる細胞があるけれど『確定ではありません』」という意味になります。細胞の変化の程度が軽度だとASC-US、重度だとASC-Hです。
一方、LSILやHSILは「明らかに異形成があります」という場合です。細胞の変化の程度が軽いとLSIL、中等度~高度だとHSILになります。
いずれの場合も、精密検査として最終的に組織診断が必要になります。まとまった細胞をとってきて、顕微鏡で見る検査です。
細胞診の結果がLSILでもHSILでも、組織診を行うことには変わりありません。検査結果を受け取ったらすぐに、婦人科を受診しましょう。
「LSIL」の精密検査後は?(横浜市 婦人科 おすすめ)
組織診の結果が「軽度異形成」であった場合は、4~6カ月ごとに定期的な検査をして経過観察するか、HPVのタイピング検査を追加します。
HPVのタイピング検査は、HPVの「何番」に感染しているのかを調べる検査です。リスクの高い番号に感染しているかどうかを調べることによって、予後(その後の進行リスク度合い)を予測しやすくするための検査です。
「軽度異形成」でHPVタイピング検査が「陰性」だった場合、リスクはとても低いので、1年後に細胞診の再検査を受ければよいことになっています。
HPVタイピング検査で、ハイリスクタイプ(16・18・31・33・35・45・52・58…など13~15種類がハイリスクに分類されています)のいずれかが陽性だった場合は、4~6カ月ごとに定期的な検査を行っていきます。
HPVが陽性でも陰性でも、「定期的に細胞診を行う」という方針には変わりなく、軽度異形成でいきなり手術に進むことはありません。
「LSIL」でがんの可能性はある?(横浜駅 評判いい 婦人科)
何気なく受けた検診で「異常があります」という結果を受け取ったら、驚いたり不安になったりしますよね。
「LSIL」だった方が、精密検査をしてみたら「がん」であったというケースは、当院では今のところ発生していません。
もちろん、LSILで精密検査をしてみたら、軽度異形成よりも進んだ病変が見つかるということはありますから、「LSILなら大丈夫」というわけではありません。
ただ、多くの場合は、LSILという結果の後に詳しい検査をしたら、「軽度異形成」という結果が返ってきます。
軽度異形成であれば、経過観察のみで大丈夫なわけですから、「自分の体や『子宮』に定期的に意識を向けるきっかけになったわ」と考えてみるのもよいかもしれません。
時々、「異常が出たら怖いから検査を受けない」という方もいらっしゃるのですが、これは「太ったよな~」と思いながら体重計に乗らないのと同じです。
現状をきちんと把握して初めて、健康を維持しやすくなります。
検査結果で、何か気になる事があれば、まずはご相談にいらしてください。
ご予約はこちらから
日付:2026年1月19日 カテゴリー:女性検診,子宮頸がん検診
子宮頚がん検診でASC-US?【横浜駅近くの婦人科】
子宮がん検診の結果はどう見る?(横浜市 評判いい 婦人科 女医 土曜日)
子宮頚がんの検診を受けても、結果の見方がよくわからないという患者様は結構いらっしゃいます。
会社の検診や自治体の検診といった検診のみの機関だと、結果だけが郵送で送られてくるパターンも多いので、「クラスⅡです。念のため半年後に再検査を受けてください」「LSILです。精密検査が必要です」といったコメントを読んでも、さっぱり意味が分からず相談先にも困るというケースもよく耳にするんですよね。
自治体の補助を使って子宮頚がん検診を受けた場合、結果の報告書が「異常なし」「異常あり」のどちらかしか書いていないこともあります。
「異常あり」であった場合は、その結果とともに、精密検査を受けるために必要な「医療機関向けの報告書」または「紹介状」がもらえます。
どのような異常なのかが詳しく知りたい場合は、検診を受けた施設に言えば、詳しい内容が書いた紹介状を発行してくれます。
人間ドックなどで、普通の健診と一緒に受けた場合、結果報告書に「ベセスダシステム」による結果が記載されていることが多いと思われます。
「ベセスダシステム」は、「クラス○」という表記方法に代わって、新しく子宮頚がん検査の結果を表記する方法です。
結果報告書に書いてある、NILM・ASC-US・ASC-H・LSIL・HSILというアルファベットが、検査の結果を表しています。
ASC-USは「グレーゾーン」?がん?(横浜市 おすすめ 婦人科 女医 土曜日)
子宮頚がんの検査結果で、一番理解しにくいのが「クラスⅢa」や「ASC-US」という結果だと思われます。
「クラスⅢa」というのは、子宮頚がん検診の結果の古い分類の仕方です。この結果の解釈の仕方は「クラス3aと言われたら」という記事で詳しくご説明していますので、そちらを参考にしてみて下さいませ。
「ASC-US」というのは、新分類・ベセスダシステムによる結果の表記方法です。細胞に変化があって、軽度異形成も否定しきれないけれど単なる炎症だけかもしれない、という微妙なグレーゾーンのことを指します。
すぐに治療が必要な可能性は低いけれど、追加の検査や精密検査が必要な場合があるレベルということになります。
ASC-USだった場合、方針としては次の3つの選択があります。
1)HPVハイリスクタイプの感染の有無を調べる
2)6ヵ月後に細胞診の再検査を受ける
3)コルポスコピーによる精密検査を受ける
このうち、1)に関しては、「ASC-US」という結果だった人に限り、HPVのハイリスクタイプがいるのかいないのかを調べる検査が保険でできます。
これは、HPV感染の有無によって細胞におきる変化に大きな差があるため、HPV感染があるかどうかを重要視するということです。
当院では、ASC-USの結果が返ってきたら、まずHPVハイリスクタイプの検査をお勧めしています。
この検査でHPVが「陰性」であれば1年後の再検査ですみますし、逆に「陽性」であればコルポスコピーによる精密検査に進みます。
無駄な検査を防ぐためにも、見落としを防ぐためにも、HPV感染の有無をはっきりさせておくと安心です。
ASC-USという結果が出た後に行う、HPVハイリスクタイプ検査は保険適用ですので、自己負担額は約1500円です。検診結果で異常を指摘されたけれど、どうしたらいいの?という方は、まずはお電話でご予約下さい。
予約専用電話045-440-5577
ご予約はこちらから
日付:2026年1月19日 カテゴリー:子宮頸がん検診
横浜市の無料クーポンが届いた方へ
横浜市の無料クーポンの有効期限は3月末です(横浜市 おすすめ 婦人科 女医 土曜日)
当院では、横浜市の子宮頚がん検診を受けていただくことが可能です。
6月末ごろから、横浜市の子宮頚がん検診無料クーポンが発送されています。
そろそろ住民の皆様のお手元に、届くころかと思われます。
今年度は、いつもより無料クーポンの対象者が拡大されています。
以下の方にクーポンが届く予定です。
★4月の時点で20歳の方(2004年4月2日~2005年4月1日生まれ)
★4月の時点で65歳の方(1959年4月2日~1960年4月1日生まれ)
★4月の時点で21~24歳で1度も横浜市の子宮頚がん検診を受けていない方
横浜市の子宮頚がん検診は2年度に1回受けられます(横浜駅近く 評判いい 婦人科 土曜日)
無料クーポンの対象年齢でなくても、30歳未満の方や61歳以上の方は、「2年度に1回」横浜市の補助を使って子宮頚がん検診が受けられます。
補助を使った場合の自己負担額は1360円です。
30歳~60歳の方は、「5年に1回」横浜市の補助を使ってHPV検診が受けられます。
詳細は、横浜市のホームページをご覧ください。
横浜市の子宮頚がん検診は何をするの?(横浜市 おすすめ 婦人科 女医 土曜日)
横浜市の子宮頚がん検診も、人間ドックや会社の健診で受ける子宮頚がん検診も、行う検査の内容は同じです。
子宮の出入り口をブラシのようなものでこすり、取った細胞で検査を行います。
検査する項目が、年齢によって異なります。
30歳~60歳の方⇒HPVの有無を調べる
上記以外の年齢の方⇒細胞の形を調べる
当院で検診を受けていただく場合の流れです。
*電話またはWebで検診の予約を取る
*初診の方は受診までにWeb問診を記入する
*当日予約時刻までに受付をする
*医師の問診を受ける
*内診を受ける
*横浜市に提出する問診票を記入する
*お会計
内診にかかる時間は、ほんの数秒です(お着換えの時間を除く)。
痛みが気になるという方が多いのですが、内診時に使用する器具のサイズを小さくしたり、深呼吸をしながら受けていただくことで、「多少の違和感」程度で受けていただくことが可能です。
子宮頚がんは、ワクチンでウイルスへの感染を予防すると同時に、検診で早期発見することがとても大事です。早期に発見できれば、子宮を温存しつつ、完治を目指せるからです。
若い方に多いがんだからこそ、必要な方は、ぜひクーポンをご活用ください。
注)クーポンが届いても男性経験がない方は検査は不要です。HPVへの接触リスクがない間は「子宮頚がんの検査」として検診を受ける必要はありません。
日付:2026年1月18日 カテゴリー:子宮頸がん検診
ASC-USやLSILの時にするコルポスコピー検査&組織検査の流れ
ASC-USやLSILの意味は?~横浜市 女医 評判いい 婦人科 駅ちか~
人間ドックや自治体検診で行われている子宮頚がん検診は、細胞をこすり取って顕微鏡で見る「細胞診」という検査です。子宮頚がん検診(細胞診)で異常を指摘された場合、精密検査として「コルポスコピー検査」と「組織検査」を行います。
正確には、
*子宮頚がん検診(子宮頸部細胞診)でASC-US+HPV検査で陽性
*子宮頚がん検診でLSIL・ASC-H・HSILのいずれかだった
場合に、精密検査に進みます。
ちなみに、子宮頚がん検診(子宮頸部細胞診)でASC-USだったけれど、追加で行ったHPV検査が「陰性」だった場合は、組織検査は必要ありません。
HPV検査が「陰性」ということは、少なくとも、現在出ている細胞の異常が、「癌になっていく可能性」が極めて低いものと判断できます。
なので、子宮頚がん検診(子宮頸部細胞診)がASC-USで、HPV検査が「陰性」の時は、「1年後に細胞診を再検査する」ということになっています。
精密検査の「コルポスコピー検査」とは?(横浜駅 近く おすすめ 婦人科 土曜日も)
「コルポスコピー検査」とは、子宮の出入り口、つまり子宮頚がんが発生する場所を拡大して観察する検査です。
通常は、コルポスコピー検査と組織検査をセットにして行います。
子宮頚がん検診で、LSILやASC-HやHSILだった場合は、HPV検査は行わず、すぐにコルポスコピー検査に進みます。
コルポスコピー検査は、あくまで、子宮の出入り口を拡大して観察するだけの検査なので、この検査だけを行っても異常の程度を正確に診断することはできません。
コルポスコピー検査を行う直前に、子宮頚部に「酢酸加工」を行うことによって、細胞に異常がある部分を分かりやすくします。
「酢酸」を子宮頚部につけると、細胞に異常がある部分が白っぽく変化したり、「モザイク」と呼ばれる模様が浮かび上がったりします。
この、酢酸加工によって浮かび上がってきた「細胞に変化が起きていそうな部分」の組織を狙い撃ちでかじりとるのが「組織検査」です。
精密検査の流れ(横浜市 婦人科 評判いい 女医 土曜日も)
コルポスコピー検査と組織検査は、およそ次のような流れで行います。
1)クスコ診で子宮頚部を見えやすくしておりものをぬぐう
2)酢酸がしみ込んだ綿球を子宮頚部に押し当てて酢酸加工をする
3)コルポスコピーで子宮頚部を拡大しながら病変部分を観察する
4)細胞に異常がありそうな部分2~3か所の組織をかじりとる
5)消毒して腟内にタンポンやカーゼを入れる
組織をとる時に、少し痛みを伴うことがありますが、通常は数秒で終わります。
酢酸加工の時間を含めても、数分で終わる検査です。
組織をとるので、ある程度出血します。
血行が良くなると検査後の出血が増える場合があるので、通常検査した当日は運動や入浴は控えます。軽くシャワーを浴びるのは問題ありません。
止血しやすくするために、タンポンやガーゼで圧迫しますので、通常は検査から数時間後にそれらを抜きます。
自分でとる場合もあれば、翌日再度受診して病院でガーゼを抜く場合もあります。
通常は、検査から2週間程度で組織診断の結果が返ってきます。
結果次第で、その後の治療又は検査の方針が決まります。
他の病院で受けた子宮頚がん検診の結果に異常があった場合も、当院でコルポスコピー検査と組織検査を承ることが可能です。
結果の見方がわからない場合のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
予約専用電話→045-440-5577
日付:2026年1月16日 カテゴリー:子宮頚がん,子宮頸がん検診
子宮頚がん検診の精密検査
職場の検診などが行われるシーズンだからなのか、子宮頚がん検診で異常を指摘された方からのお問い合わせが増えています。
検診の結果の見かたについては過去の記事を参考にしていただけるとわかりやすいかと思います。
子宮頚がん検診で異常を指摘された場合に行う精密検査は、「HPV検査」か「コルポスコピー検査と組織検査」です。
HPV検査は、子宮頚がん検診を行う時と同じように子宮の出口を少しだけこする検査です。細胞診の結果が「ASC-US」だった場合にに必要になります。痛みや出血はほとんどありませんし、検査は数秒で終わります。だいたい1週間くらいで検査結果が分かります。この検査で「陽性」つまりウイルスがいますよという結果だった場合は、さらに「コルポスコピー検査と組織検査」が必要になります。
コルポスコピー検査というのは、拡大鏡で子宮の出口の状態を観察する検査です。見るだけなので、この検査だけでは精密検査にはなりません。コルポスコピーで子宮の出口の状態を観察し、細胞の変化が強そうな部分を狙って組織をとるのが「組織検査」です。細胞をある程度まとまってかじり取るので、多少の痛みや出血を伴います。細胞の変化の程度をしっかりと観察するので、検査は5~10分くらいかかります。組織検査の結果は10~14日くらいで分かります。
当院では、HPV検査もコルポスコピー検査と組織検査も承ることが可能です。検査の所要時間が異なるために、ご予約の際に子宮頚がん検診の結果を確認させていただいております。ご予約をご希望の場合は、お手元に検診結果をご用意いただいてからお電話いただくとスムーズです。
ご予約はお電話でのみ承っております 予約専用電話045-440-5577
がん検診を受けるとがんになる?!
最近、初診時に明らかにがんだと診断しなければいけないケースが続きました。
どなたも共通しているのが、これまでに1度も検診を受けていないか5年以上検診の間隔があいてしまっていることと、症状が出てから受診されるまでに数ヵ月が経っているという点です。
どちらも、がんを早期発見するために必要なことと、真逆の行動なのは言うまでもありません。
命に関わるようながんにならないようにするためには、予防できることは予防する・定期的な検診を受ける・気になる症状が出たらただちに受診する、という事が重要です。
子宮頸がんの場合だと
予防する=性交開始年齢を遅くする・ワクチンを打つ
検診を受ける=年に1度の細胞診または3年に1度の細胞診とHPV検査を受ける
症状が出たら=不正出血やおりものが気になったら受診する
ということになります。
自然療法派の方の中には、検診を受けると返ってがんになるから検診は受けない、という方もいらっしゃるようですが、検診を受けていない事ががんの発見を遅らせてしまうことは、実際の症例から火を見るより明らかです。
検診を受けないという選択をするのは個人の自由ですが、検診を受けない方がよいと人に勧めるのは明らかに間違いです。
検診は「がんになったらどうしよう」と不安に思いながら受けるものではありません。「健康であることを確認する」ために受けるんです。そして、万が一異常が見つかっても、それが命に関わるようなレベルになる前に対処できるから意味があるのです。
もちろん、検診や健診の結果の見方によっては、不要な心配を増やしたり、病気を自ら作り出してしまうことになる場合もあります。検診を受けることが問題なのではなくて、どこからを「異常」と判断するか、結果の読み方の問題です。
子宮頸がんの細胞診による検診は、色々ある検診の中でも最も受ける意味がある(がんの予防につながる)検診としてランク付けされています。自分の子宮を大切にするなら、自分の子宮を信じているのなら、きちんと年1回のがん検診を受けましょうね。
日付:2015年9月24日 カテゴリー:子宮頸がん検診
HPV感染と子宮頸がん
今月は、自治体が配布している無料クーポンの使用期限が切れる月なので、「駆け込み検診」の患者様が増えていますね。クーポンが検診のきっかけになって異常が見つかるケースは、案外少なくありません。クリニックでも、普通に毎年検診を受けている方より、クーポンで検診を受ける方の方が異常が出る割合が多かったりします。
子宮頸がん検診で異常が出ると、しばしば質問されるのがHPV感染との関係です。子宮頸がんの原因のほとんどは、HPVへの感染なので、細胞に異常が出ているということはHPVに感染している可能性が高いと言えます。HPVに感染しているかどうかは、HPV検査をすればすぐにわかります。
みなさんが一番気にされるのは、このHPVがどこから感染したものなのか、そして今後HPVが「消えてくれるのか」ということです。HPVは性交渉によって感染するものなので、今までの性交渉の誰かから感染したものということは言えますが、誰からなのかを特定することは困難ですし、また特定する意味もありません。一度感染すると体から完全にいなくなることはないので、HPVを「退治する」ことを考えるのはあまり意味がありません。
HPVは性交渉の経験がある女性の約8割が一生に一度は感染することがあるくらい、ある意味ありふれたウイルスです。私はよく、「子宮頸部の『風邪』みたいなものだ」とご説明しています。
つまり、感染機会を持つところからがんになるまでの経緯を風に例えると理解しやすいのです。
*HPVに感染している人との性交渉=風邪をひいている人との接触
風邪をひいている人のそばにいたからと言って全員にその風邪がうつるわけではありません。でも、手洗いやうがいやマスクなどでできるだけ感染しないように予防はします。
HPVに感染している人と性交渉を行っても必ず感染するとは限りませんが、ワクチンやコンドームでの予防は大事です。
*HPVへの感染=風邪がうつる
予防をしていても風邪がうつることはあります。でも、ほとんど症状が出ないこともあれば、軽い症状で終わることもあります。
HPVへ感染しても、ただウイルスが「いる」というだけで細胞に何も変化が起きない場合もあります。HPV感染が「性感染症(STD)」ではないと言われるのは、感染したこと自体はまだ「病気」とは言えないからです。
*HPVが細胞に変化を引き起こす(異形成)=風邪症状が出る
風邪がうつった人の一部は、しっかり風邪症状が出ることがあります。でも、早めの治療を行ったり、自分の免疫力を高めればすぐに症状は改善し、重篤な病気を引き起こすまでには至りません。
感染したHPVが細胞に変化を引き起こしてくるとがんの手前の「異形成」という状態になります。この段階ではまだ「がん」ではないので、変化が軽い「軽度異形成」や「中等度異形成」であれば、自分の免疫力を高めてウイルスの活動を抑えることで、細胞が正常化していくことが期待できます。変化の強い「高度異形成」であっても、円錐切除という手術(早期治療)で完治できます。
*HPVによる細胞の変化がさらにひどくなってがんになる=風邪をこじらせて肺炎になる
本来風邪は、早めの治療できちんと対応すれば重篤な状態になることはありません。自然に治るものです。でも、対応が遅れたり極端に免疫力が下がったりしていると、「こじらせた」状態になって肺炎などの重篤な状態につながる場合があります。
「異形成」の状態がさらに進むと「上皮内がん」を経て「浸潤がん」へと進行していきます。この状態にまで進んでしまうと、大掛かりな手術や放射線治療などが必要になってきます。HPVに感染した人の約1000人に1人が、何もしなければがんまで進行していきます。この状態まで進行しきる前に「早期治療」できるようにするのが、検診の役割なのです。
子宮頸がんは、ワクチン接種と適切な検診で必ず予防できるものです。
「めんどくさい」なんて言わずに、毎年しっかり検診を受けてくださいね。
日付:2015年3月12日 カテゴリー:子宮頚がん,子宮頸がん検診,日々の雑記