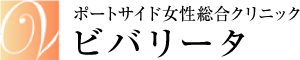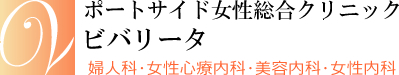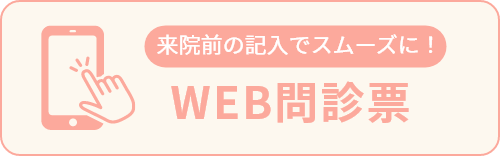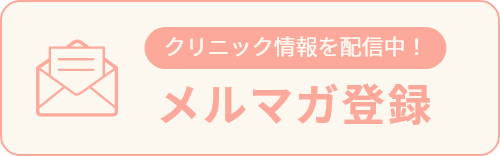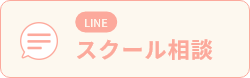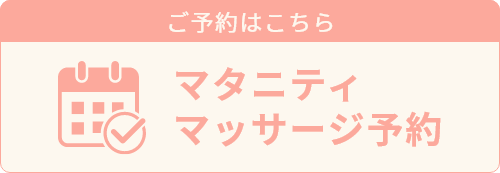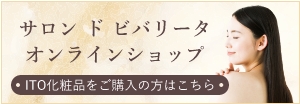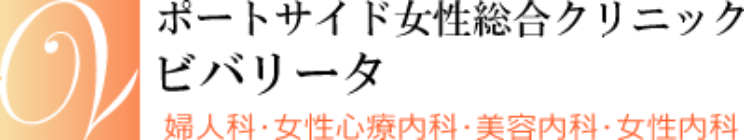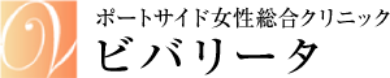日々の雑記
横浜市の子宮頚がん検診無料クーポン対象年齢について【横浜市の婦人科】
がん検診が無料で受けられるチャンスです!(横浜駅 おすすめ 近くの 婦人科)
横浜市の子宮頚がん検診は、20歳以上の横浜市に住民票がある方が受けられます。
現在は、
20歳~29歳および61歳以上の方⇒2年ごとの細胞診(自己負担額1360円)
30歳~60歳の方⇒5年ごとのHPV検査(自己負担額2000円)
が横浜市の補助を使って受けられる子宮頚がん検診です。
いずれも、横浜市と契約している医療機関で受けることが可能です。
当院も提携医療機関になっておりますので、がん検診をご希望の方はネットまたはお電話でご予約ください。
これらの補助以外に、これまでは「4月の時点で20歳の人」に「無料クーポン」が配布されていました。
今年度では、2004年4月2日~2005年4月1日生まれの方が無料クーポンの対象です。
さらに、今年度は、がん検診を受けていない方や以前クーポンが届いた時は内診が困難な状態であったためクーポンが使用できずに期限が過ぎてしまった方を対象に、「これまで一度も横浜市の子宮頚がん検診を受けていない21歳~24歳の人」にも無料クーポンが配布されることになりました。
無料クーポンが届いたらすぐにご予約ください!!(横浜駅 評判いい 近くの 婦人科)
無料クーポンは、6月末ごろの発送予定とのことですので、7月中には届くと思われます。
クーポンが届く前でも、下記の条件に当てはまる方は無料で子宮頚がん検診が受けられます。
<無料になる条件>
*生年月日2000年4月2日~2004年4月1日
*これまでに一度も横浜市の補助を使って子宮頚がん検診を受けていない
クーポンが届いた後は、クーポンの提出が必ず必要になります。
クーポンを待たずに早めに無料検診を受けたい方は、ご自身が対象に当てはまっているかをご確認の上ご予約ください。
また、クーポンが配布された後(8月以降)は必ずクーポンをご持参ください。
子宮頚がん検診は痛いの?(横浜駅 近くの 婦人科 女医)
初めて子宮頚がん検診を受ける方は、「どんなことをするの?」「痛いのでは?」とご不安が強いかと思われます。
子宮頚がん検診は、子宮の出入り口の細胞をブラシでこすり取る検査です。クスコという器具を入れて、子宮の出入り口を見えやすくして検査をします。検査にかかる時間は「数秒間」です。
小さなクスコを使って、リラックスした状態で受けていただければあっという間に終わりますし、それほど痛みを感じることもありません。
緊張が強かったり、検査の時に力が入ってからだが内診台から持ち上がってしまうと、見たい場所が見えなくなり、時間もかかるし痛みも出やすくなります。
できるだけリラックスして受けていただけるようにお声かけしながら検査をいたしますのでご安心ください。
日付:2026年2月13日 カテゴリー:日々の雑記
座るだけで骨盤底筋トレーニング?!【横浜駅近くの婦人科】
「座るだけ」の筋トレチェア(横浜 ビジリス 安い)
骨盤底筋も下半身の筋肉も一緒にトレーニングしたい方必見!
実は多い「尿もれ」の悩み
「30代女性の6割」この数字、何のデータなのか分かりますか?
2023年7月に花王フェムケアラボがWEBで行ったアンケート調査の結果です。なんと、回答者の約8割が「尿もれの経験がある」、30代女性の約6割が「現在尿もれに悩んでいる」と回答しています。
ところが、尿もれ経験者の約半数が「特に理由はないが相談したことがない」と回答しているのです。
クリニックの診療でも、膀胱炎症状をご相談なさる方はいらっしゃいますが、尿もれについてのご相談は本当に稀です。産後の方や、更年期の方に、「排尿のトラブルはありますか?」とこちらから伺うと、「実は…」とおっしゃるケースがほとんどなのです。
実際に伺ってみると、尿もれだけではなく、「度々トイレに行きたくなる」「尿意を感じると我慢しきれなくなる」「トイレが近くて旅行や長距離の移動が不安」と言ったお悩みがたくさん出てきます。
尿もれの原因は?(横浜 骨盤トレーニング 安い)
そもそもなぜ尿もれやトイレが近いといったトラブルが起きるのでしょうか?
もちろん、ホルモンの異常や細菌感染などが原因となることもあります。
そして、多くの場合、「骨盤底筋群のゆるみ」が原因で上記のような様々なトラブルが引き起こされています。
骨盤底筋群は、小さな筋肉がいくつか集まって骨盤の「底」を支えています。ちょうどハンモックのように薄い筋肉が骨盤の一番下の部分を作っており、その筋肉が骨盤内の臓器を支えています。膀胱も骨盤内にある臓器のひとつで、骨盤底筋群がゆるむと膀胱の位置が下がりやすくなります。
また、骨盤底筋群の一部は、尿の出口・腟の出入り口・肛門をそれぞれ「閉める」という働きを持っています。そのため、この骨盤底筋群が緩むと、尿が出ないように出口を「閉めておく」ことができなくなり、その結果尿もれが起きやすくなります。
骨盤底筋群のゆるみが引き起こすトラブル(横浜 婦人科 評判いい)
骨盤底筋群は様々な機能を持っています。
例えば・・・
*骨盤内の臓器を支える
*尿や便がもれないように出口を閉めておく
*膀胱の働きを助けて尿を出し切る
*直腸の働きを助けて便を出し切る
これらの働きが弱くなることで、次のようなトラブルが起きやすくなります。
*子宮や腟が下がってくる(飛び出てくる)
*直腸が下がってくる(飛び出てくる)
*くしゃみをしたり重いものを持った時に尿がもれる
*度々トイレに行きたくなる
*尿意を感じたらすぐにトイレに駆け込まないと間に合わない
*便秘や残便感
*パートナーとのスキンシップの質が落ちる
骨盤底筋群にダメージが起きる原因(横浜駅 おすすめ 婦人科 女医)
骨盤底筋群がゆるむ原因はいくつかありますが、最近は出産経験がなくても筋力が低下している人が増えてきている印象です。実際に、20代で尿もれを経験している方のほとんどが、出産経験のない人です。
★お産の回数が多い
★大き目の赤ちゃんを産んだことがある
★便秘がちでいつも強くいきんで排便している
★急いで排尿することが多くお腹に力を入れて無理矢理排尿している
★重いものを持つことが多い
★内臓脂肪が多い
★重いものを持った状態でスクワットなどの筋トレをしている
これらの、いずれか一つでも当てはまっていれば、骨盤底筋群に負担がかかっている可能性があります。
骨盤底筋群を鍛えるには十分な筋トレが必要(横浜市 婦人科 女医)
もし、上記のようなトラブルがある場合は、まずは婦人科や泌尿器科で相談してみることをお勧めします。
状態によっては、骨盤底筋群のダメージが大きすぎて、手術が必要なケースもあります。
ただ、多くの場合は、そこまでひどくはなく、骨盤底筋群の「筋力」を取り戻せばある程度トラブルが解消する可能性が高いのです。
つまり、必要なのは「筋トレ」です。
ではどのくらいの「筋トレ」をすればいいのでしょうか?
「骨盤底筋体操」という、骨盤底筋群を鍛える体操があります。体操と言っても、全身を動かす体操ではなく、骨盤底筋群をギュッと締めるという小さな動きを繰り返すものです。
この骨盤底筋体操をどのくらいすると効果が得られるかというと・・・
*1セット30回
*合計1日4セット以上(朝、昼、夜、就寝前)
*約3か月間毎日続ける
どうでしょう?あなたはこのトレーニングを欠かさず3か月間継続できそうでしょうか?
多くの患者様は、トレーニングの仕方をお伝えしても、「継続して行う」ことが難しいとおっしゃいます。効果が得られる前に、挫折してしまう方がほとんどなのです。
20分間椅子に「座っているだけ」(横浜 評判いい スターフォーマー 婦人科 女医)
では、この「筋トレ」を、「ただ椅子に座っているだけ」で行えるとしたらどうでしょうか?
筋肉を鍛えるためのトレーニングは、自分の「脳」から指令を出して動かした場合と、電気や電磁波の刺激で動かした場合とでは、同じように効果が期待できます。
今回クリニックに導入した骨盤底筋トレーニングチェアは、椅子の座面から筋肉を刺激する電磁波パルスが出るため、「ただ座っているだけ」で骨盤底筋がギュッと収縮して、筋トレをしているのと同じ状態を作ることが可能です。
しかも、15分間座っているだけでスクワットに換算すると約1万回行ったのと同じくらい、筋肉への刺激が伝わります。
そのため、20分間「ただ座っているだけ」で、週2回ずつのトレーニングの場合では8~10回で効果が感じられるようになるのです。
効果を感じていただくために3回まで体験価格!(横浜 評判いい婦人科 スターフォーマー)
骨盤底筋トレーニングチェアは、保険診療による「治療」ではありません。
そのため、自費でのご案内になります。
通常、初回体験価格でのご案内は1回限りのことが多いのですが、1回では十分効果を感じていただけないかもしれないため、3回まで体験価格でご利用いただけるようにいたしました。
★★★★★★通常価格 体験価格
10分 2000円 1000円
20分 3800円 2000円
30分 5600円 3000円
ご予約・お問い合わせはクリニックまで⇒045-440-5577
#婦人科 #横浜 #尿もれ #骨盤底筋
日付:2026年2月11日 カテゴリー:日々の雑記
ピルを休薬しないで飲み続けるとどうなる?【横浜駅近くで評判の婦人科】
ピルの種類は?おすすめのピルは?(横浜 評判いい 婦人科 ピル 安い)
月経困難症つまり生理痛の治療薬として発売されているピルには「低用量」と「超低用量」があり「超低用量」のピルには「周期投与」と「連続投与」という2種類の服用方法が選択できるタイプがあります。
「連続投与」は、3~4か月間ピルをずっと飲み続ける服用方法です。
周期投与タイプ
→ルナベルULD(フリウェルULD)・ジェミーナ21錠・ヤーズ(ドロエチ)
連続投与タイプ
→ヤーズフレックス・ジェミーナ21錠+28錠
「周期投与」は、「周期的に月経様出血(消退出血と言います)を起こす」方法で服用するという意味です。21日間実薬を服用し、7日間休薬するか、24日間実薬を服用し4日間偽薬を飲むことによって、28日サイクルで定期的に消退出血を「来させ」ます。
一方、「連続投与」は、実薬を服用する期間を引き延ばすことによって消退出血の間隔を28日よりも延長して「年間の出血回数を減らす」方法です。要するに、ピルを休薬せずに飲み続けるということです。
ピルを飲み続けている間は、生理が止まった状態になりますので、3~4か月間ピルを続けて飲めば、その間生理を止めていることになります。要するに、ピルで生理を3か月くらい止めておくことができるということですね。
具体的には、実薬を77日間続けて飲んで7日間休薬するタイプと、実薬を最長120日まで続けて飲んで4日間休薬するタイプがあります。簡単に言うと、消退出血の回数を年間3~4回に減らすことができることになります。
どの種類や服用方法が適しているのかは、「ピル処方の流れ」の中の「3:医師との面談」の時に、直接医師と相談します。
ピルを休薬せずに飲むメリット(横浜市 おすすめ 婦人科 女医)
「周期投与」つまり休薬期間を設けて飲むメリットは、「生理が毎月来る」ことです。出血が定期的に来ることで安心感を覚える方にとっては、「周期が整う」というメリットがあります。
また、毎月出血を確認することで「妊娠していないことの確認」をしている人にとっても、周期的に出血があることが安心につながるでしょう。
しかし、医学的には毎月出血を「わざわざ来させる」メリットはなく、むしろ、トータルの出血量が増えたり、毎月痛みを感じることによるデメリットの方が大きくなる可能性があります。
実際、内膜症のリスクはトータルの出血量と比例して高くなるというデータもありますので、毎月出血を来させるより、ピルを続けて飲んで年間3~4回の出血で済ませた方が内膜症リスクも減らすことができるのです。
「連続投与」つまり休薬せずに飲むメリットは、出血回数を減らせるということです。ピルで生理がこないように止めておくので、休薬した時だけ出血します。
出血回数が減れば、月経前後の不調を感じる回数も減り、貧血も予防でき、内膜症リスクも下げることができます。
また、休薬期間に何らかの不調が出る場合も、「連続服用」の方が不調が出る回数を減らすことが可能です。例えば、休薬期間に起きる出血で、腹痛や腰痛がつらい場合や、休薬期間に情緒不安定になったり頭痛が起きたりする場合です。
デメリットとしては、連続服用している途中で不正出血が起きてしまうことがあるという点です。長期間服用し続けることによって、途中の不正出血は起きにくくなりますが、患者様のお話からの印象ですと、飲み初めの3~6カ月間は「3シート連続しようと思ったけれど途中で出血してしまった」といったことが起こりうる様です。
ヤーズフレックスは最長120日まで連続服用ができますが、飲み始めて半年くらいは、120日続かずに出血してしまうことの方が多いようです。「ヤーズフレックスを120日飲み続けようと思ったけれど途中で出血してしまった」という場合は、必ずしも異常ではないので、何日サイクルが自分にとって最適なのかを探っていくとよいでしょう。
ヤーズフレックスは「フレキシブル服用」ができます。そのため、ヤーズフレックスを連続服用していたら途中で出血してしまったという場合、出血した時点でいったん4日間の休薬をとってリセットし、再度連続服用を再開することができます。
ずっと飲み続けていると、だらだら不正出血して不快という場合は、いったん休薬を挟んでみることをお勧めします。
どのくらいまで飲み続けると出血が起きるのか、自分のリズムがつかめてくると、思わぬ出血が起きる前に休薬をとったりしてうまくコントロールしていけます。
休薬期間の情緒不安定や頭痛も軽減(横浜駅 おすすめ 近くの 婦人科 女医)
ピルを休薬せずに飲むメリットは、単純に出血の回数が減るというだけではありません。
休薬期間中は、多少ですが血液中の女性ホルモンの量が下がります。つまり、ホルモンの「波」ができてしまうのです。
これによって、休薬期間中に情緒不安定になったり、頭痛や吐き気が起きたりする場合があります。
また、休薬期間中に、いったん脳への「ホルモンが十分ありますよ」という信号が途絶えることになるので、脳から卵巣へ「卵を育てなさい」という命令が出やすくなります。
休薬せずに飲み続ければ、この「脳からの命令」も抑えたままになりますので、女性ホルモンの量が変動しにくくなりますし、すり抜け排卵のリスクも抑えることができます。
つまり、ピルを休薬せずに続けて服用することは、いろんな点でメリットがあるのです。
休薬しないと「血がたまる」?(横浜市 評判いい 婦人科 ピル)
ピルを休薬せずに飲むと、本来休薬中に出るはずの出血がないわけですから、人によっては「どんどん子宮の中に血がたまってしまうのでは?」と心配になるかもしれませんね。
よく、「出血が来ない間は子宮の中に『不要なもの』がたまっていくのですか?」ということを質問されますが、ピルの働きとして出血の元となる「内膜」を「厚くさせない」という効果があります。なので、飲み続けている間も子宮の中に内膜が「たまらない」ようにしているのです。
実際、28日周期で出血を来させていた時よりも、ピルを休薬せずに連続服用した時の方が出血量が減ってきたという方の方が多いので、「3カ月出血を止めていたら3か月分たまりにたまった分がどっと出るのではないか」という心配は不要です。
毎月出血を来させる方が、「デトックス効果がある」というのも、大きな誤解ですので、ピルは休薬せずに飲んでも大丈夫です。
ただし、連続服用タイプのピルであっても、添付文書で定められている77日または最長120日までという服用期間は守る必要があります。
何のために、3~4か月に1回は休薬することになっているのかというと、万が一ピルを服用中に「気づかずに妊娠」していた場合に、休薬中の出血が来ないことでその妊娠に気付くことができるようにするためです。
逆に言えば、性行為の経験がないなどの、「絶対に妊娠していない」と言い切れる場合は、休薬を全くせずにピルを飲み続けても、何も問題ないということになります。
もちろん、添付文書に記載している期間を超えて飲み続けることは、基本出来にはできません。イレギュラーな飲み方をする場合は、医師と相談しながらになります。
ピル処方の流れ・内診はいらない?(横浜 おすすめ 婦人科 女医)
当院では、すべての種類のピルを処方しています。服用の目的やご本人のご希望を伺いながら、どのピルにするかを相談して決めていきます。
ピルの種類も徐々に増えてきていますから、ぜひご自身のライフスタイルに合ったピルをチョイスしてみてくださいね。
一般的なピル処方時の流れは、次のような手順になります。
1)問診票の記入
2)血圧測定
3)医師との面談
4)必要に応じて検査(超音波検査やホルモン採血など)
5)ピルの服用方法や副作用の説明
6)お会計
避妊目的でピルを処方する場合は、4番目の検査は不要です。
生理不順で処方する場合は、超音波検査とホルモン検査(採血)が必要です。
生理痛で処方する場合は、超音波検査と場合によっては腫瘍マーカーの検査(採血)が必要になります。
ピルの種類や服用方法は、3番目の医師とお話しする際に相談できます。
◆◆『マイナビクリニックナビ』で「ピル処方のオンライン診療におすすめのクリニック7選」として当院が掲載されました◆◆
★★ピル処方のオンライン診療におすすめのクリニック7選【2025年最新】★★
リンク先URL:https://clinic.mynavi.jp/article/telemedicine_oc-lep/
日付:2026年2月10日 カテゴリー:日々の雑記
新しい横浜市子宮頚がん検診についてよくあるご質問【横浜駅近く女医の婦人科】
★2025年1月から横浜市子宮頚がん検診が変わりました(横浜駅 おすすめ 婦人科 土曜日)
*30歳未満・61歳以上は今まで通り
*30歳~60歳(2025年4月1日の時点で)の方は
・補助が使える年齢が5年ごとの節目年齢(30歳・35歳・・・)
・検査の方法が「HPV単独法」
・自己負担額は2,000円
・以下の方は検診の対象外となります
ア:子宮頚部を有さない方
イ:子宮頚部浸潤癌の治療中又は過去なったことがある方
ウ:異形成や上皮内がんなどの「前がん病変」の経過観察中の方
エ:性交経験が一度もない方
・横浜市から届いたバーコードを持参する
(バーコードがないと検査ができません)
注)節目年齢ではないのに検診用バーコードが届くことがあります
2025年1月から移行するため最初の5年間は節目年齢ではない方にも案内が届きます。 2024年4月~12月の期間に横浜市の子宮頚がん検診を受けている節目年齢ではない方は、バーコードが届いても検査を受けられるのは2026年4月以降になります。
質問1:案内が届いたらすぐに受けないといけませんか?(横浜市 おすすめ 婦人科 女医 土曜日)
2024年4月~12月に横浜市の補助を使って子宮頚がん検診を受けている方は、届いたバーコードで検診を受けられるのは2026年4月以降です。
それまでは、バーコードをなくさないように保管しておいてください。
前回の検診が2024年3月より前であればいつでも検査は可能です。
特に、ここ2~3年検診を受けていないという方は、お早めに受けることをお勧めします。
質問2:筋腫の手術で子宮をとっていますが検査は可能ですか?(横浜 評判いい 婦人科 女医)
子宮をすべて取っている(子宮全摘を受けている)方は、上記「対象外になる方」の「ア:子宮頚部を有さない方」に該当します。
そのため、子宮全摘後は横浜市の補助を使用して子宮頚がん検診を受けることはできません。
一般的に、良性疾患(子宮筋腫や子宮腺筋症)で子宮全摘をした後は、「子宮がん検診」が不要になります。
質問3:過去に子宮頚がん検診で異常が出たことがありますが検査は受けられますか?(横浜駅 女医だけ 婦人科 評判いい)
現時点で、まだ異常が残っており、「異形成」を経過観察中の方は横浜市の補助を使った検診をご利用いただくことはできません。
過去に「異形成」を指摘されて、現在は完全に正常に戻っている場合や、「異形成」で手術を受けてその後ずっと正常な場合は、検査が可能です。
完全に正常に戻っているかどうかが分からない場合は、「過去2回分の検査結果が『NILM』かどうか」をご確認ください。
質問4:HPVが陽性だともう一度検査を受けないといけないのですか?(横浜 駅近く 婦人科 女医)
検診の結果で、HPVが陽性だった場合は「自動的に」細胞診が追加されます。そのため、再度検査にお越しいただく必要はありません。ウイルスの検査のためにぬぐい取った検体でそのまま細胞診を行います。
また、検査代金に細胞診が追加になった場合の料金も含まれているため、細胞診が追加になっても追加の料金はかかりません。
質問5:HPV単独検診は5年ごとにですが本当に5年間もあけて大丈夫でしょうか?(横浜 ベイクウォーター クリニック)
今回の横浜市の検診事業の目的は、「進行した癌で命を失うことを防ぐ」ことが目的です。そのため、「できるだけ早い段階で異常を見つける」ことが目的にはなっていません。
つまり、5年前の検査が「異常なし」でも、5年後に検査を受けた時に「異形成です」「早期のがんです」という結果になる可能性はあるということです。
例え検診で異常がなくても、不正出血やおりものの異常があれば、その段階で細胞診を受けるようになさってください。
日付:2026年2月10日 カテゴリー:日々の雑記
生理不順だと妊娠しにくい?【横浜市で評判の婦人科】
生理不順はどの年代でも起こりうる?(横浜 年末年始 婦人科 おすすめ 女医)
クリニックにいらっしゃる患者様の訴えの中で、一番多いのは生理不順や生理以外の出血です。
ご年齢は10代の方から50歳前後の更年期世代まで様々・・・生理が始まったばかりの思春期も、閉経が近づいてくるプレ更年期も、生理不順になりやすい年齢ではあります。年齢によって、生理不順になる原因は異なりますが、生理不順になる年代は意外と幅広いのです。
最近は、ストレスや冷えやすい生活の関係か、本来であれば一番ホルモンバランスが安定しているはずの20代~30代の方にも、生理不順で悩まれる方が増えている印象です。本来なら、一番妊娠する確率が高い年代ですが、生理不順だと妊娠しにくくなる可能性があります。生理不順で妊娠できる確率がどのくらいであるかは、生理不順の程度や原因によりますので、必ずしも「生理不順だから妊娠できない」というわけではありません。
生理不順のパターンは色々ありますが、周期が安定しない・少量の出血がダラダラ続くといった症状が多く見受けられます。
どこからが生理不順?45日は正常?ほっといていい?(横浜市 婦人科 評判いい 女医)
正常な生理の基準は、25~38日周期とされています。普段は30日前後で生理が来ているけれど、年に1~2回40日くらいになることがある、という程度であれば問題ない範囲の乱れである可能性が高いでしょう。
逆に、周期は25~38日の範囲に入っているけれどばらつきが大きく、ごく少量の出血で終わることもあるという場合は、無排卵の可能性もあります。1~2か月基礎体温をつけてみて、体温がずっと低いままであれば、婦人科で相談することをお勧めします。
また、「急に体重が減った後に生理が来なくなった」「精神科で処方された薬を飲み始めたら生理が乱れた」「徹夜続きで体調を崩したら出血が止まらなくなった」など、明らかに生理不順の原因に心当たりがある場合は、様子を見ずに早めに受診した方がいいでしょう。
その他に、受診した方がいい生理不順の基準は、
*生理の周期が24日未満または45日以上
*生理が1~2日で終わる
*基礎体温をつけても体温がずっと低い
*3か月以上生理が来ない
といったケースです。
特に、今すぐに妊娠したいと考えている人で、周期のばらつきが気になる場合や、基礎体温が低いままの場合は、早めに受診することをお勧めします。
生理不順だと妊娠しにくい?不妊になる?(横浜市 婦人科 年末年始 女医)
20代~30代の生理不順の場合、よく聞かれるのが「このままだと妊娠しにくかったりしますか?」というご質問です。すぐに妊娠を希望しているわけではなくても、「生理不順だと妊娠しにくいかも」という漠然とした不安は抱えやすいようです。
ホルモンのアンバランスや無排卵は不妊の原因になりますから、生理不順を放置していれば妊娠しにくくなる可能性はあります。
逆に、生理不順だからといって妊娠しないわけではありませんから、妊娠を希望していない方は必ず避妊が必要です。
生理不順だと、妊娠する確率がこのくらいです、という明確な数値はありません。そもそも、生理不順ではなくても、20~30代の健康な女性の妊娠率が「1年間で85%」というかなりアバウトな算出しかできないのです。
生理不順の原因にも色々あり、一番頻度が高く、「妊娠しにくさ」につながる原因は、「多のう胞性卵巣症候群」です。「多のう胞性卵巣症候群」は、排卵がうまくいかなくなるために、生理の周期が不規則になったり、中途半端な出血がダラダラ続いたりしやすくなります。
男性ホルモンが高くなることも多く、生理不順以外に、ニキビや多毛などの「男性化兆候」を伴うことも少なくありません。
また、体重が減ったことによる無月経=体重減少性無月経の場合も、この状態を放置してしまうと、妊娠しにくさにつながる可能性があります。
体重減少が原因の場合は、まず適切な体重に戻すことが重要となりますので、婦人科的なアプローチだけではなく、精神科や内科的な治療を総合的に行っていく必要が出てくる場合も少なくありません。
生理不順の治療法は?ピルは使える?(横浜市 評判いい 婦人科 女医)
生理不順の方が妊娠を希望されている場合、漢方でホルモンバランスを整えたり、排卵誘発剤できちんと排卵するサイクルに導く治療が中心になります。生理不順で排卵していない場合は、妊娠しにくいというより妊娠を目指すことができませんので、「いかにして排卵させるか」が治療のポイントになります。
排卵誘発剤は、使い方によっては多胎のリスクが発生するので、治療への反応がイマイチな場合は、不妊治療専門機関で治療した方が安全です。
そこまで妊娠を急いではいないけれど、妊娠希望はある方の場合、排卵を促す前に3ヶ月ほどピルで卵巣を休ませてホルモンバランスを整えることもあります。遠回りに感じられるかもしれませんが、その方が、スムーズに排卵しやすくなったりすします。
また、高プロラクチン血症や甲状腺機能異常のせいで生理不順になっている場合は、妊娠を目指すことを前提に、これらのホルモンを整えていきます。場合によっては、ホルモンが正常化しても、妊娠が成立するまでホルモンを抑えたり補ったりする薬を継続するケースもあります。
生理不順でも妊娠できる?(横浜 おすすめ 婦人科 女医)
生理不順だからといって、必ずしも妊娠できないまたは妊娠しにくいわけではありません。
ただ、異常に気付かずに放置してしまうと、妊娠しにくさにつながってしまう可能性はあります。
適切な治療を行うことや、現状を把握しておいて、将来妊娠したいと思った時にどのような対処が必要なのかをあらかじめ知っておくことが、安心して妊娠を目指すことにつながります。
生理が毎月きちんと来ない、少量の出血が10日以上続く、月に2回生理が来る・・・といった症状がある方は、お早めにご相談くださいませ。
【横浜の婦人科】ご予約はこちらから
産後の尿漏れは治らない?!【横浜ベイクウォーター近く女医の婦人科】
産後の尿漏れは誰もがなりうる?(横浜市 評判いい婦人科 女医)
産後に尿漏れを経験する人は少なくありません。様々なデータがありますが、産後数日以内に尿漏れを経験する人は30%以上であり、そのうちの45%の人は産後3か月たっても尿漏れが続いていたという報告もあります。
「いつまで尿漏れが続くの?」「半年たっても尿が途中で止められないのは異常?」「尿漏れは何かに行けばいいの?」といった不安を抱える方も少なくありません。
産後に尿漏れが起きやすくなる条件としては、
*分娩回数が多い
*経腟分娩(特に吸引分娩や鉗子分娩)
*妊娠中の体重増加が8㎏以上
*出産時のBMIが24以上
*高齢出産
などが挙げられます。
産後の尿もれのタイプ(横浜駅近く おすすめの婦人科)
産後の尿漏れにはいくつかのパターンがあります。
★腹圧性尿失禁
立ち上がろうとした時や、くしゃみをした時など、お腹に力を入れた時に漏れてしまう尿漏れです。
お腹にかかる圧力で、膀胱が圧迫された時に、圧迫の力に負けてしまって尿が漏れ出てしまうのがこのタイプです。
★切迫性尿失禁
突然の尿意を感じて、すぐにトイレに駆け込まないと漏れてしまうパターンです。
通常は徐々に感じるはずの尿意が、突然強く発生し、尿意を感じてから排尿してしまうまでの時間が短いために間に合わなくなるのがこのタイプです。
★混合性尿失禁
腹圧性と切迫性の両方の場合に漏れるというタイプです。少しでも尿がたまると漏れてしまうかもしれないという不安から、たびたびトイレに行ってしまい、尿漏れと頻尿が一緒に発生することもあります。
産後の尿漏れはなぜ起きる?(横浜 婦人科 女医 おすすめ)
産後の尿漏れの原因は、ほとんどが妊娠中や分娩による「骨盤底筋」のダメージです。特に、経腟分娩の場合、分娩時に骨盤底筋に大きな力が加わるので、筋肉が不可に負けて緩んでしまいがちです。
骨盤底筋群は、小さな筋肉がいくつか集まって骨盤の「底」を支えています。ちょうどハンモックのように薄い筋肉が骨盤の一番下の部分を作っており、その筋肉が骨盤内の臓器を支えています。膀胱も骨盤内にある臓器のひとつで、骨盤底筋群がゆるむと膀胱の位置が下がりやすくなります。
また、骨盤底筋群の一部は、尿の出口・腟の出入り口・肛門をそれぞれ「閉める」という働きを持っています。そのため、この骨盤底筋群が緩むと、尿が出ないように出口を「閉めておく」ことができなくなり、その結果尿もれが起きやすくなります。
産後の尿漏れを改善する方法(横浜市 婦人科 評判いい)
産後直後は尿漏れが気になっていても、3~4か月で自然に改善していくケースがほとんどです。ただ、完全に元に戻らなかったり、ずっと尿漏れが続いてしまうこともあるため、産後から積極的に骨盤底筋を鍛えることが推奨されています。
「産褥体操」や「骨盤底筋体操」と呼ばれる筋トレが、尿漏れの改善にも有効です。お産した病院によっては、産後から助産師さんが「産褥体操」を教えてくれるところもあります。
特にトラブルがなく、正常なお産をした方であれば、産後すぐに産褥体操をしても大丈夫ですので、早めに筋トレを開始して、骨盤底筋の働きを取り戻しましょう。
産後の尿漏れがなかなか改善しない時は?(横浜駅 婦人科 女医 おすすめ)
産褥体操をしっかりして、体重のコントロールもできていれば、多くの方が3か月程度で尿漏れは気にならなくなっていきます。
もし、3か月たっても十分に改善しない場合や、骨盤底筋体操が上手にできない場合は、婦人科又は女性泌尿器科で相談してみるのもよいでしょう。
骨盤底筋体操の効果を十分に得るためには、かなりの頻度で筋トレをし続ける必要があります。
効果的な筋トレの目安は、
*1セット30回
*合計1日4セット以上(朝、昼、夜、就寝前)
*約3か月間毎日続ける
産後に赤ちゃんのお世話もしながら、こんなに筋トレはできない・・・という方もいらっしゃるかもしれませんね。
20分間椅子に「座っているだけ」(横浜 婦人科 おすすめ)
では、この「筋トレ」を、「ただ椅子に座っているだけ」で行えるとしたらどうでしょうか?
筋肉を鍛えるためのトレーニングは、自分の「脳」から指令を出して動かした場合と、電気や電磁波の刺激で動かした場合とでは、同じように効果が期待できます。
今回クリニックに導入した骨盤底筋トレーニングチェアは、椅子の座面から筋肉を刺激する電磁波パルスが出るため、「ただ座っているだけ」で骨盤底筋がギュッと収縮して、筋トレをしているのと同じ状態を作ることが可能です。
しかも、15分間座っているだけでスクワットに換算すると約1万回行ったのと同じくらい、筋肉への刺激が伝わります。
そのため、20分間「ただ座っているだけ」で、週2回ずつのトレーニングの場合では8~10回で効果が感じられるようになるのです。
効果を感じていただくために3回まで体験価格!
骨盤底筋トレーニングチェアは、保険診療による「治療」ではありません。
そのため、自費でのご案内になります。一般的な、骨盤底筋トレーニングチェアの費用は、病院にもよりますが5000円~15000円です。ちょっとハードルが高いかもしれません。
そこで、まずは気軽に試していただけるよう、体験価格をご用意しました。
通常、初回体験価格でのご案内は1回限りのことが多いのですが、1回では十分効果を感じていただけないかもしれないため、3回まで体験価格でご利用いただけるようにいたしました。この機会にぜひお試しください。
★★★★★★通常価格 体験価格
10分 2000円 1000円
20分 3800円 2000円
30分 5600円 3000円
ご予約・お問い合わせはクリニックまで⇒045-440-5577
横浜市の補助を使った子宮頚がん検診の変更点【横浜駅近く女医の婦人科】
★横浜市の子宮頚がん検診が変わりました(横浜 評判いい 婦人科)
横浜市の補助を使った子宮頚がん検診についていくつか変更点があります。
*2025年1月から30歳~60歳の人にHPV検診が導入されました
*2025年4月以降にこれまで20歳だけに配布されていた無料検診のクーポンが「今まで一度も子宮頚がん検診を受けたことのない25歳までの方」にも配布されます。
★これまでの横浜市子宮頚がん検診(横浜駅 おすすめ 婦人科 土曜日)
*対象は20歳以上
*補助が使える年齢は特定されておらず「2年度に1回」
*検査の方法は「子宮頚部細胞診」
*自己負担額は1,360円
*20歳ちょうどに配布されるクーポン以外は検査時に持参するものはない
★2025年1月からの横浜市子宮頚がん検診(横浜市 おすすめ 婦人科 土曜日)
*30歳未満・61歳以上は今まで通り
*30歳~60歳(2025年4月1日の時点で)の方は
・補助が使える年齢が5年ごとの節目年齢(30歳・35歳・・・)
・検査の方法が「HPV単独法」
・自己負担額は2,000円
・以下の方は検診の対象外となります
ア:子宮頚部を有さない方
イ:子宮頚部浸潤癌の治療中又は過去なったことがある方
ウ:異形成や上皮内がんなどの「前がん病変」の経過観察中の方
エ:性交経験が一度もない方
・横浜市から届いたバーコードを持参する
(バーコードがないと検査ができません)
注)節目年齢ではないのに検診用バーコードが届くことがあります
2025年1月から移行するため最初の5年間は節目年齢ではない方にも案内が届きます。 2024年4月~12月の期間に横浜市の子宮頚がん検診を受けている節目年齢ではない方は、バーコードが届いても検査を受けられるのは2026年4月以降になります。
★検査後の流れ(横浜駅 婦人科 おすすめ 女医)
HPV検査の結果が → 陰性 ⇒次の節目年齢にHPV単独検診
↓
陽性
↓
自動的に子宮頚部細胞診追加 → NILM ⇒1年後HPV単独検診
↓
NILM以外 ⇒ 精密検査
★ご予約はお電話またはWebで承っております(横浜駅 おすすめ 婦人科)
緊急避妊薬が薬局で手に入る?
緊急避妊薬(アフターピル)とは何か(横浜市の婦人科)
緊急避妊薬とは、一般的にアフターピルとも呼ばれる、性交後に服用することで妊娠を阻止する薬です。一般的な避妊薬は事前の予防に用いられますが、緊急避妊薬は一定の時間内に服用すれば性交後の妊娠を防ぐことが可能です。
その効果は、性交後24時間以内に服用すれば95%以上、72時間以内でも89%とされています。ただし、緊急避妊薬は避妊法の選択肢の一つであり、あくまで非常措置であることを理解する必要があります。日常的な避妊法として使用するものではありません。
緊急避妊薬の主な成分(横浜駅近くの婦人科)
主成分であるレボノルゲストレルは、妊娠を防ぐ働きをもつプロゲステロンと呼ばれるホルモンの一種です。通常、排卵後に卵巣に残った黄体という組織からプロゲステロンが分泌され、その作用が着床を促します。
しかし、レボノルゲストレルによりプロゲステロンの作用が阻害されると、卵子の着床が阻止され、妊娠を避けることが出来るのです。
緊急避妊薬の作用の仕方(横浜市の婦人科)
緊急避妊薬の主な働きは、主成分レボノルゲストレルが卵管の運動を抑制し、精子の通過や卵子の移動を遅らせることにより、受精を阻止します。
もし既に受精が起こっていても、子宮内膜の状態を変化させ、卵子の着床を阻むことで妊娠を防ぐ働きをします。そのため、性交後すぐに服用することで、オーバリーコーパスリューテウムの生成を抑制し、卵子の着床場所確保を難しくします。
緊急避妊薬の使用シーン(横浜駅近くの婦人科)
緊急避妊薬はあくまで非常時の措置でありますから、コンドームの破裂や避妊具の失敗、または性的暴力を受けた場合など、予期せぬ状況後の避妊法として使用されます。
この薬は性交後72時間以内に服用することが必要であり、できるだけ早く服用すれば効果が高まるとされています。性交後すぐに医療機関へ相談することが重要です。
ただし、この薬は絶対的な避妊成功を保証するものではありませんので、日常的に避妊を行う方法を、適切な医療機関で相談することが最も望ましいでしょう。
薬局で緊急避妊薬を買える?(横浜市の婦人科)
緊急避妊薬、通称アフターピルは避妊に失敗した場合や性交後に予期せぬ妊娠を避けるために使用されます。しかし、どのようにして手に入れることができるのでしょうか。
以前は、医師の処方せんなしに薬局で緊急避妊薬を買うということはできませんでした。2023年11月20日以降、条件を満たした一部の薬局で、試験的に処方箋なしの購入が可能になりました。
現在はまだ、この「一定条件を満たした薬局」でしか、医師の処方箋なしで手に入らず、必要な人が簡単にアクセスできるという状態にはなっていません。
これに対して、あすか製薬が、緊急避妊薬である「ノルレボ」を市販薬として販売できるよう厚生省に承認申請をし、承認されました。
これによって、2月2日から研修を受けた薬剤師が常駐している薬局で、医師の処方せんなしに緊急避妊薬を購入できるようになります。
どの薬局で購入できるのかについては、厚生労働省のホームページに掲載されています。
このリストは大変見づらいので、溝口ファミリークリニックのスタッフの方が、
緊急避妊薬の入手可否から個人輸入まで、詳しく解説していきます。
緊急避妊薬の入手方法(横浜駅近くの婦人科)
日本では緊急避妊薬は処方箋医薬品であり、一部の診療所やクリニックでしか取り扱われませんでした。つまり、これまでは、薬局での購入は、前述の「試験的な取り組みとして認可された薬局」以外では、原則として不可能でした。
また、ネット通販での個人輸入も一部制限はあるものの許されています。どちらの方法も一定の条件や制約がありますので、詳細は後述の「薬局の選び方」、「個人輸入について」をご参照ください。
緊急避妊薬処方薬局の選び方(横浜市の婦人科)
2026年2月2日以降は、下記リストにある薬局であれば、医師の診察を受けなくても緊急避妊薬を購入することが可能です。
まだ、全国すべてのエリアで可能になっていないため、近隣の薬局がリストに載っていない場合は、近くのクリニックを受診した方が早い場合があります。
そのため、必要な時に直接購入できる場所として、避妊に関する専門知識を持ったクリニックや診療所を選ぶことが重要です。また、遠方や診療時間内に行けない場合には、電話やインターネットで相談できる機関を探すことも一つの方法です。
個人輸入について(横浜駅近くの婦人科)
緊急避妊薬の個人輸入は、日本の薬事法により一定の制限の元許されています。また、個人輸入業者を使えば日本国内にいながらも購入することが可能です。
ただし購入する際も注意が必要で、個人輸入業者の選び方、輸入方法、商品の評価など、様々な項目を確認してから購入しなければなりません。また、間違った選択をすると粗悪な商品を手に入れてしまう可能性もあるため、安全な購入のためには調査・確認が不可欠です。
薬事法や法令遵守の観点からも、個人輸入の際には必ず信頼性のある業者を選ぶようにしましょう。
緊急避妊薬の正しい使用法(横浜市の婦人科)
緊急避妊薬、一般的には「アフターピル」と呼ばれるものですが、一体どのような薬なのか、正しい使用法とは何なのでしょうか。不安を抱える方も多いことでしょう。ここでは、アフターピルの基本的な知識と、その正しい使用法を学んでいきましょう。想定外の事態に備え、正確な知識を身につけることが大切です。
【服用タイミング】
アフターピルの服用タイミングは、性交後すぐにでも摂取可能です。しかし、最も効果的なのは、性交後72時間以内に服用することです。とはいえ、72時間を過ぎてからでも、120時間以内であれば服用可能です。
ただし、時間が経つほど効果は減少することを理解しておくべきです。性交後、速やかにアフターピルを服用することをお勧めします。また、服用するタイミングや薬の種類によっては、月経周期がずれる可能性があります。適切なタイミングでの服用は、不要な心配や混乱を避けるために重要です。
【薬剤の正しい摂取方法】
アフターピルは、基本的に水またはぬるま湯と一緒に口から服用します。服用に際して、空腹時や食後など、特定のタイミングは必要ありません。ただし、ごく稀に服用後に吐き気を感じる方がいますが、この場合は食後に服用すると緩和されることがあります。
そして大事なことは、一度服用した後、2時間以内に嘔吐した場合、効果が低下する可能性があるため吐き気を抑えておく必要があります。もし嘔吐した場合は、追加で服用すること、または医療機関に相談することをお勧めします。
【重複服用の対処法】
アフターピルを重複して服用した場合、特に深刻な副作用が発生する訳ではありません。しかし、吐き気や頭痛などの軽度な副作用が強まる可能性があります。重複服用を避けるには、服用回数や服用時間をきちんと記録しておくことが重要です。
万が一、重複服用してしまった場合は、無理をせず安静にして、症状がひどい場合には医療機関に相談しましょう。また、正しい知識を持つことで、不安感を軽減し、適切な対応を取ることができます。
緊急避妊薬の注意点(横浜市の婦人科)
突発的で避けられない性交渉などが原因で適切な避妊ができなかった際、後から避妊を行う「緊急避妊薬(アフターピル)」が有効です。しかし、その効果だけではなく、副作用や禁忌症、長期間の使用による影響も理解して使用する必要があります。
誤った知識や先入観から、必要な時に活用できないケースもあるのです。以上を踏まえ、有意義な避妊法として活用するためには、その利用の仕方とリスクも把握することが重要となります。
【副作用と対処法】
アフターピルの効果を発揮するためには、女性ホルモンを一時的に大量に体内に取り込むことになります。その結果、吐き気や頭痛などの身体的不快感や、心身の不調を引き起こす場合もあります。
吐き気を予防するためには、薬を服用する前に軽い食事をとると良いでしょう。また、服用後に強い頭痛が続く場合は、速やかに医療機関を受診するようにします。いずれにせよ、副作用が続く場合には早急に医師に相談することが必要です。
【注意すべき禁忌症】
体調や病歴によっては、緊急避妊薬の服用が推奨されないケースもあります。特に、肝疾患や乳癌、血液疾患などの持病がある方は、緊急避妊薬を服用することで症状が悪化する可能性があるからです。また、アレルギー反応を引き起こす場合もあるため、自己判断で服用せず、必ず医師と相談してから使うようにしましょう。緊急避妊薬は、本来副作用がとても少ない薬です。適切な使い方を知ることで、健康を損なうことなく緊急避妊薬を活用することが可能となります。
【長期間の使用とその影響】
一般的に緊急避妊薬は、あくまで「緊急」時のためのもので、定期的・長期間の使用は推奨されていません。頻繁に使用するとホルモンバランスを乱し、月経異常を引き起こす可能性があります。また、肝臓に負担をかけるため、病気のリスクが高まる可能性もあるのです。長期間使う必要があるなら、避妊用のピルなどの通常の避妊薬を検討してみると良いでしょう。医師と相談して最適な避妊法を選ぶことが大切です。
緊急避妊薬の費用と保険適用(横浜市の婦人科)
緊急避妊薬は、性交後すぐに使用することで避妊効果が期待できる薬です。ただし、現在日本で発売されている価格は、海外と比較すると非常に高価で、特に若い方にとっては費用面のハードルも高くなってしまっている可能性があります。
では、具体的にはどの程度の費用がかかるのでしょうか。また、保険は適用されるのでしょうか。そして、費用を抑える方法はあるのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。
【緊急避妊薬の価格】
緊急避妊薬の価格は、薬剤の種類や取得方法などにより異なります。緊急避妊用の薬である「ノルレボ」は、医師の処方せんが必要であり、15000円前後の費用がかかります。ジェネリックである「レボノルゲストレル」でも、8000円前後かかります。
費用が比較的高いため、金銭的に負担が大きいと感じる人もいるでしょう。
また、最近では、緊急避妊薬を低価格で提供するインターネット通販もありますが、偽物や品質の低い薬を警戒すべきです。
【保険での対応状況】
避妊に関する投薬・検査はいずれも保険が使えません。そのため、緊急避妊薬の購入費用は保険適用外となります。
性被害にあったために、緊急避妊薬が必要になった場合は、所定の手続きをとることで公費負担で緊急避妊薬を処方してもらうことが可能になります。
保険適用ではありませんが、本人負担はなくなります。
緊急避妊薬の市販薬化がもたらす影響(横浜市の婦人科)
緊急避妊薬の市販化がもたらす影響は大きいと予想されます。導入に際しては、個人の健康面に関わるものから、社会全体の避妊文化に影響を与えることまで、幅広い視点からその影響を考える必要があるのです。
【個人の健康面での影響】
緊急避妊薬は、不適切な避妊、避妊失敗後の自己判断による利用を可能にします。これは一見、女性の権利と健康を守る方策に見えますが、実際には副作用に起因する潜在的な健康リスクが存在します。これらの薬は一時的な避妊手段であり、連続的な使用は推奨されません。そのため、2010年の世界保健機関(WHO)の指導では、緊急避妊薬は月に2回以上使用すべきではないとされています。
また、これらの薬を自己判断で使用すると、結果として性感染症の危険性を増大させる恐れがあります。緊急避妊薬は避妊の失敗を補うものであって、性感染症の予防には役立ちません。そのため、これらの薬品を適切に使用できない個々の状況では、定期的に医師の診察が受けられる方がメリットが大きい場合もあります。
【社会的な影響】
一方、社会的な影響についても考慮する必要があります。避妊についての理解と意識は、社会全体の避妊文化や性教育に広範に影響を及ぼすからです。緊急避妊薬の一般的な利用の増加は、避妊についての誤解や混乱を引き起こす可能性があります。これにより、一部の人々が誤った情報に基づいた選択をすることがないように対策を立てる必要があります。
また、緊急避妊薬が一般に広く普及すると、これについてのより包括的な教育が必要になります。しかし、それは多くの国や地域で性教育が十分に行われていない現状を考慮すると、より簡単に必要な避妊にアクセスできるようにするのと同時に、十分な性教育を受ける機会を用意することが重要です。
【避妊文化の変化】
最後に、緊急避妊薬の普及がもたらすはずの最大の変化は、避妊文化そのものに見ることができます。これらの薬を自由に利用できることにより、人々は自分自身の性的健康と行動についてより責任を持つようになるでしょう。しかしこの選択が自己判断に任されると、ある程度の教育と理解が必要になります。
緊急避妊薬の導入は、避妊文化に新たな視点を提供します。それは自己決定と自由競争の観点から、また社会全体の健康と福祉の観点からも重要ですが、そのバランスを取ることが重要でしょう。
その他の避妊方法と比較(横浜市の婦人科)
避妊方法は多種多様に存在します。その中で、コンドーム、ピル、子宮内避妊器具などがよく知られています。各避妊方法は、その特性と利便性によって個々のライフスタイルや体質、健康状態に合ったものを選択することが重要です。
以下では、これらの避妊方法との比較について詳しく解説していきます。
【コンドームとの比較】
コンドームは男性が身につけることで、性行為時の避妊に使用されます。正しく使用すれば、避妊効果は高いと言われています。また、性感染症から身を守る役割も有します。
これに対し、ピルや子宮内避妊器具は避妊効果のみが目的です。特に、子宮内避妊器具は設置から取り外しまで医師の介入が必要なため、準備や使用には専門的な知識と時間が必要です。これらの点から、コンドームは手軽に導入できる避妊法と言えるでしょう。
【ピルとの比較】
ピルとは、女性がホルモン剤を服用する避妊方法です。ピルは避妊効果が高く、服用を正しく続ければほぼ100%近い避妊効果があります。しかし、ピルの使用には医師の指導が必要で、継続的な服用が求められ、一部の人には副作用の可能性もあります。
緊急避妊薬は服用時のみの避妊効果ですが、ピルは継続的な避妊効果を得ることが可能です。
【子宮内避妊器具との比較】
子宮内避妊器具とは、子宮内に直接装置を設置し、避妊を行う方法です。一度装置を設置すれば数年間にわたって避妊効果が続くので、持続的な避妊を望む人にお勧めです。また、間違った使い方をする可能性がほぼなく、避妊効果も極めて高いとされています。
しかし、挿入や取り外しには医療専門家の介入が必要であり、体質により適用できない場合もあるため、全ての人に適するわけではありません。それに対して、コンドームやピルはそれぞれ特性を理解しさえすれば、誰でも容易に導入できるという利点があります。
緊急避妊薬の市販薬化が必要な理由(横浜駅近くの婦人科)
緊急避妊薬、一般的にはモーニングアフターピルとも呼ばれています。その役割は、性交後すぐに服用することで、妊娠を避けることが可能となるというものです。
しかし、日本では導入が遅く、広く知られていません。また、医師の処方箋が必要という条件が、特に若い方にとってはアクセスしにくくなる要因となっています。
性教育における知識の普及、急な妊娠によるリスクの回避、避妊の手段としての重要性、それらを考慮すると、この緊急避妊薬の市販薬化は一段と必要性が増してきています。
【避妊の重要性】
避妊の重要性については、ある一定の認識が社会に存在しますが、まだまだ深化させていく余地があります。避妊は、ただ性病から身を守る手段、または不意の妊娠を避けるためだけではありません。それは、女性自身の身体と向き合い、自らの身体と生活を守るという行為です。
性交渉は二人の意志によるものであり、その結果を二人が共有するものであるべきでしょう。それは避妊の観点からも共有すべきであり、その役割は緊急避妊薬にも求められています。
【妊娠と出産のリスク】
妊娠と出産には大きなリスクが伴います。例えば、十分な準備のない妊娠は、母体の健康に影響を及ぼすだけでなく、生活やキャリアにも大きな影響をもたらします。さらに、妊娠による身体や精神の変化は、女性だけでなく周囲の人々にも影響を及ぼします。
したがって、予期しない妊娠は避けるべきであり、そのための手段として緊急避妊薬の存在が重要となります。
【性教育への意義】
性教育は、単に避妊方法や性感染症の予防について教えるだけでは足りません。それは生涯にわたる知識であり、健やかな性のあり方、相手を尊重する心構えを身につけるためのものです。
そこで、この教育に避妊薬の存在を取り入れることは、適切な知識と意識を身につけるために不可欠です。性教育の一環として、緊急避妊薬の存在とその用法、効果などをしっかりと教えることで、より心地良い性生活を送るためのヒントを与えていきます。
ピルの種類と値段 副作用のでかたは異なる?【横浜駅近くの婦人科】
ピルの種類は何種類?(横浜 評判いい婦人科 保険ピル処方)
現在「月経困難症」の治療薬として発売されている、保険適用薬のピルは以下の種類があります。これらのピルは、「月経困難症」の治療目的で使用する場合は保険で処方することが可能です。
実際は、「月経困難症」だけではなく、月経不順やPMSやニキビの治療目的で使用する場合も、保険適用になっていることがほとんどです。保険適用であれば、避妊用の自費のピルより安くピルを購入することが可能です。
★()内はジェネリック
ルナベルLD(フリウェルLD)
ルナベルULD(フリウェルULD)
ヤーズ(ドロエチ)
ヤーズフレックス
ジェミーナ
アリッサ
一方、保険がきかない自費のピルは、「避妊目的」で使用するピルです。
現在日本で使用できる避妊用のピルは
トリキュラー21または28(ラベルフィーユ)
マーベロン21または28(ファボワール)
の実質2種類です。
ピルの種類は、服用の目的や出ている症状によって医師が選ぶことが多いですが、自分でリクエストすることもできます。
保険適用のピルと自費のピルの違い(横浜市 評判いい 婦人科)
ピルの種類には、「保険適用されるもの」と「自費でしか処方できないもの」があります。最大の違いは、「避妊目的」で使用できるのは自費のピルであるという点です。保険適用のピルを避妊目的で処方することはできません。
純粋に避妊のみの目的でピルを処方してもらう場合は、自費のピルから選択することになります。
一方、生理痛や生理不順の治療でピルを使う場合は、保険適用のピルでも自費のピルでも処方することが可能です。保険適用のピルの方が、安く購入することができますし、ホルモン量が少ない「超低用量ピル」を選択することができるので、通常は治療目的でピルを服用する場合は保険適用のピルを処方してもらうことがほとんどです。
自費と保険では、費用の自己負担額が異なります。
自費のピルは、値段を各病院が自由に決めることができるため、病院によって価格が異なります。だいたい、1シート(1月分)が2500円~3500円くらいの病院が多いようです。
ちなみに当院では、自費のピルは一般の方が1シート3000円、学生さんは1シート2000円です。
保険適用のピルは、厚生省が決めた値段で処方されますので、どの病院で処方してもらっても1シートの値段は同じです。
ピルの種類によって異なりますが、保険証が3割負担の場合では、先発薬品だと2000~2500円、後発薬品だと700~850円くらいです。
ピルの種類は?(横浜駅 近く 評判いい 婦人科)
ピルの分類は、「含まれているホルモン量」「含まれている黄体ホルモンの種類」「飲み方の違い」によって分類できます。
★含まれているホルモン量による分類=低用量と超低用量
ピルの中に含まれている「卵胞ホルモン」の量が50μg以下のものが低用量で、30μg以下のものが超定量用です。
低用量ピル=トリキュラー(ラベルフィーユ)・マーベロン(ファボワール)・ルナベルLD(フリウェルLD)
超低用量ピル=ルナベルULD(フリウェルULD)・ヤーズ(ドロエチ)・ヤーズフレックス・ジェミーナ
天然型エストロゲンピル=アリッサ
★含まれている黄体ホルモンの種類による分類=第1世代~第4世代
ピルに含まれている「黄体ホルモン」の種類によって、第1世代から第4世代まで分類されています。黄体ホルモンの種類の違いは、むくみやニキビの出やすさと関係しています。
第1世代=ルナベルLD・ULD(フリウェルLD・ULD)
第2世代=トリキュラー(ラベルフィーユ)・ジェミーナ
第3世代=マーベロン(ファボワール)
第4世代=ヤーズ(ドロエチ)・ヤーズフレックス・アリッサ
★飲み方の違い=周期投与か連続投与
ピルは基本的に4週間に1回出血が来るように、偽薬を服用するまたは休薬期間を設けて服用します。毎月生理が来るような飲み方を「周期投与」と言います。
これに対して、出血が来る回数をできるだけ減らして、負担を軽くした服用方法が「連続投与」です。連続投与できるピルは、ヤーズフレックスとジェミーナの2種類です。
ヤーズフレックスは、最大120日まで連続服用が可能です。120日薬を飲んで、4日間休薬をとります。4か月に1回しか出血が来ないので、生理の度に痛みが気になる人や、出血量を減らして貧血を予防したい場合にとても有効です。
ジェミーナは、77日間連続服用して1週間休薬をとります。3か月に1回の生理にできるということですね。
ピルの種類による副作用の違い(近くの婦人科 評判いい 女医)
ピルの種類によって「よい・悪い」があるわけではありません。どちらかというと、個人に「合う・合わない」があります。ピルが合わない場合、吐き気やむくみなどの不快な症状が続くことがあります。
飲み初めに不快な症状が出ても、1~2週間すると治まってくることが多いので、飲み始めてすぐに「ピルが合わない」と判断するのは少しもったいないかもしれません。吐き気止めやむくみを改善する漢方などを併用しながら、まずは1~2サイクル飲んでみることをお勧めします。
一般的に、ホルモン量が少ないほど頭痛や吐き気は起きにくくなります。逆に、ホルモン量が少ないほど、不正出血の頻度が多くなります。
黄体ホルモンが、第1世代や第4世代のものの方が出血量が減りやすいので、それによって痛みも軽くなることが多いのですが、必ずしも出血量と痛みの程度が連動しない場合もあります。
男性ホルモンを抑えたり、むくみを改善したりする作用があるのが、第4世代の黄体ホルモンです。
なので、むくみやニキビが気になっている人の場合は、ヤーズ(ドロエチ)が適しているケースが多いと言えます。しかし、他の種類よりヤーズを服用したときの方が肌荒れが気になるとおっしゃる方もいらっしゃるので、どのピルが一番合うのかは試してみなければわかりません。
ピルの種類を変更する場合の注意
ピルは、初めて服用する時が、最も血栓症リスクが高い状態です。通常は3か月以上継続的に服用しているうちに、血栓症リスクが徐々に下がって安定していきます。
ピルの種類を変更すると、この血栓症リスクが「初めて飲むとき」と同じレベルに戻ります。なので、種類を変更した時も、変更後3か月間は最も血栓症リスクに注意が必要な期間となります。
いろんな種類を試して、一番合うピルを見つけるのが良いのですが、あまり頻繁に種類を変更すると、ずっと血栓症リスクが高い状態になってしまいますので注意が必要です。
ご予約はこちらから