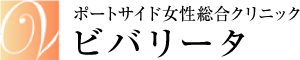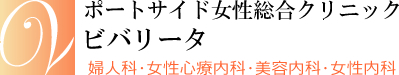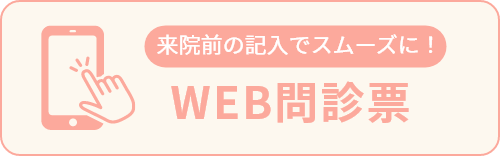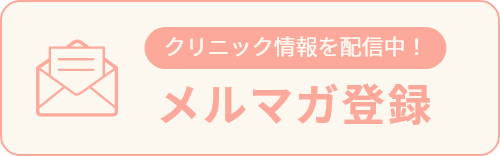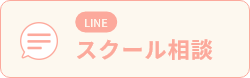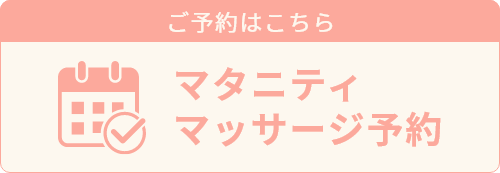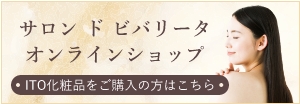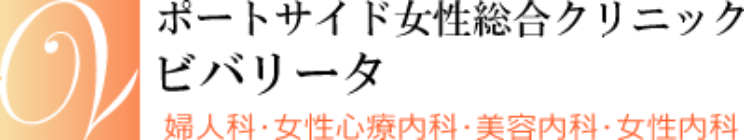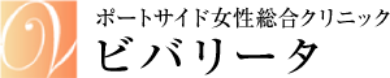婦人科の病気
妊娠中のトラブル~情緒不安定~
妊娠中~産後にかけては、ホルモンの影響を受けて情緒不安定になったり気分が落ち込みやすくなったりします。
マタニティーブルーとか産後うつはよく聞くかと思いますが、産後だけでなく妊娠中も精神的に不安定になりやすいんです。
よくある症状は、ちょっとした体調の変化にも過敏になってあれこれ心配事が増えたり漠然と不安になったりする・涙もろくなってコントロールができなくなる・イライラなどの気分の波が自分で抑えられなくなる・気分が落ち込んでふさぎがちになる、などです。
いずれも程度が軽ければ「妊娠中はよくあること」とやり過ごして問題ありません。日常生活に支障をきたすほどの状態であれば、カウンセリングや漢方で治療した方がいい場合もあります。
感情のコントロールが難しくなったら、「妊娠中なんだから仕方がない」とある程度割り切って、無理してコントロールしようとしないことも大切です。
涙が止まらないようなら気のすむまで泣くと案外スッキリしたりもします。
また、カウンセリングで自分の状態を聞いてもらうだけでも落ち着く事が多いので、ちょっと辛いなと思ったらカウンセラーに相談してみるのもいいでしょう。
日付:2011年4月15日 カテゴリー:妊娠中のトラブル
妊娠中のトラブル~むくみ~
妊娠中は黄体ホルモンという月経前に増える女性ホルモンが普段の何倍も出るため、どの期間もむくみやすくなります。また、循環する血液の量を増やすためにいつもより血液が薄まった状態になるのでさらにむくみが出やすい状態になります。
特に、妊娠後期は、大きくなった子宮が血管を圧迫して血液やリンパの流れが悪くなりやすいので、夕方になると足がむくむという方は多いですね。
基本的に、夕方や夜にかけてむくみが出るけれど、一晩寝れば元に戻っている場合は心配ありません。寝る時に足を少し高くして寝るようにしたり、お風呂上りに足の裏や足首から膝裏に向けてなで上げるようにマッサージするといいですよ。
マッサージの時に、むくみに効果的なアロマオイルを使うとさらにスッキリします。
入浴時に、シャワーで熱めのお湯と水を交互にふくらはぎに当てて水圧と温度差でマッサージするのも効果的です。
昔は「妊娠中毒症」の症状の中に「むくみ」が入っていました。なので、妊婦健診の時に毎回足のすねを押されてむくみをチェックされるんです。
今は「妊娠高血圧症」という名称に変わり、血圧と尿蛋白がチェックポイントとなったため、むくみがあるというだけでは異常とは言えないこともあります。
注意しなければいけないむくみは、朝になっても全くひかなかったり、手や顔までパンパンに腫れたようになる場合です。手が握りにくいようなむくみがあり、体重が急激に増えていたり尿量が減っている場合は病院に相談するようにしましょう。
むくみがあまりにも辛いという場合は、「サロン・ド・ビバリータ」でマタニティーマッサージを受けていただくことも可能です。
サロンのマタニティーメニューは、私自身が妊娠してから様々な「プチ不調」が出て困った時に、どこにも駆け込めるところがなくて「妊娠初期から気軽に通えるサロンが欲しい」と思って加えたものです。少しでもマタニティライフを快適にするお手伝いができたらいいなと思います。
日付:2011年4月13日 カテゴリー:妊娠中のトラブル
妊娠中のトラブル~便秘~
妊娠中は次のような様々な原因で便秘がちになります。
*ホルモンの影響で腸の動きが鈍くなる
*つわりなどで充分な水分・食物繊維がとりにくくなる
*運動を控えがちになる
*子宮が大きくなると腸を圧迫されて通りが悪くなる
基本的な対処法は妊娠していない時と同じです。
水分をしっかり摂る・食物繊維の多い食事を摂る・ヨーグルトや乳酸菌飲料を摂る・適度な運動をする・3~4日出ないようなら便秘薬を使うといった事を心がけてみて下さい。
つわりの症状が落ち着いていれば、主食を玄米にしてお野菜を中心とした食事にすることと水を1日1.5リットル以上飲むようにするといいでしょう。
ただ、妊娠中はあまり運動できなかったり、どんなに生活や食事を改善しても便秘になってしまうことがあります。あまり何日も出ないと、硬い便を出す時にお腹に余計な力がかかったりしますので、早めに薬で改善しておくことをお勧めします。
便秘薬のなかには、妊娠中に飲まない方がいいものもありますから、便秘薬を飲むときは産科で処方してもらった方が安心です。
日付:2011年4月11日 カテゴリー:妊娠中のトラブル
妊娠初期のトラブル~流産~
妊娠21週6日までの間に何らかの理由で妊娠の継続ができなくなった状態を「流産」と言います。
完全に赤ちゃんの成長が止まってしまったり子宮の外に妊娠の組織が出てきてしまった場合が狭い意味の「流産」で、出血やお腹の痛みなどが出現して「流産しかかっている状態」が「切迫流産」です。
切迫流産の主な症状は出血と下腹部痛です。妊娠のごく初期の切迫流産は薬による治療もできないので、基本的に安静にする事が一番の治療という事になります。
週数や状態によっては、止血剤や子宮の収縮を抑える薬を使ったり、入院してしっかり安静が保てるようにする事もあります。
流産の中でも、さらに細かく分類された言い方があります。
初期流産=流産の中でも妊娠初期(12週まで)の流産
完全流産=自然に妊娠組織が全て子宮外に出た場合
進行流産=自然に妊娠組織が出かかって出血が続いている場合
稽留流産=胎児心拍は止まっているが妊娠組織が子宮内にとどまっている場合
最も多くみられるのは、初期の稽留流産です。少量の出血や腹痛が出ることもありますが、自覚症状が全くなく受診してみたら胎児心拍が見えないと言われるケースも珍しくありません。
初期の流産は、約7分の1の確率で起きるので、一般の方が想像するより多いものなのです。原因のほとんどは偶発的におきる染色体の異常で、予防できるものではありません。
流産はご本人にとっては非常にショックが大きいことが多く、何がいけなかったのかと自分を責めがちですが、食べ物や生活習慣のせいではなく受精卵の染色体異常によるものですから、心配する必要はありません。
流産を3回以上繰り返す場合は「習慣流産」といって、免疫機能やホルモンに原因となる異常がないか検査をしたり、流産予防の治療をする対象となります。
日付:2011年4月10日 カテゴリー:妊娠中のトラブル
つわり~体験談版~
私の場合、つわりの症状が出始めたのは、ちょうど6週0日からでした。それまでは胸の張りやむくみはあっても、気持ち悪さは全くなかったので安心していたのですが、その日の診療が終わる辺りから車酔いのような症状が出てきたんです。
翌日には吐きたいのに吐けないといった気持ち悪さになり、普段の食事が摂れなくなってしまいました。
幸い、つわりの期間中一度も吐く事はなかったんですが、食欲はかなり落ちましたね。
時期的に7月の終わりから8月にかけての最も暑い頃だったので、暑さによる気持ち悪さも加わって、2~3週間はちょっとバテ気味でした。水分をこまめに摂ろうとしても、いつものように水が飲めず、朝起きた時は低血圧でフラフラ・・・という感じです。
野菜ジュースが比較的飲みやすかったので、ちょこちょこと口にするように心がけていました。
6週から7週の2週間くらいが気持ち悪さのピークで、その時期は冷奴と梅干が主食に。おそうめんも食べられなくはないのですが、めんつゆのわずかな甘みすら吐き気を誘うんですよね。
空腹になっても気持ち悪さがひどくなるので、仕事の時は、一口大の塩がきいた梅ムスビをラップに包んで白衣のポケットに入れておき、2時間おきくらいにつまみ食いするようにしていました。
8週に入ると症状はだいぶ落ち着いてきて、あっさりしたものなら少しずつ食べられるようになってきましたが、甘いものは臭いすら受け付けず・・・甘いものが食べられるようになったのは10週を過ぎてからでした。
つわりの期間中、トータルで3キロほど体重が減ったので、勤務先のナースたちにはちょっと心配されていたようです。
つわりの時期は臭いにも敏感になって、タバコや香水の臭いはもちろんのこと、トイレの芳香剤や洗濯洗剤の臭いも一切受け付けず。自分が使っているシャンプー・リンスは無香料なので問題なかったんですが、主人が使っているものがフローラル系の香料だったのでお風呂上りの主人にも近づけなくなって困りました(笑)
臭いで一番辛かったのは、実は患者さんの香水やタバコの臭いです。診療しながらハンカチで覆うわけにもいかず、不自然に遠ざかるわけにもいかず・・・きっと待合室にいらっしゃる妊娠初期の方も同じ思いをなさっているはずですから、病院を受診する時には香水は控えていただくように注意を促した方がいいなと改めて感じました。
私の場合はつわりの期間が3~4週間ですんだので、つわりの程度としては軽い方ですね。
ちょうど症状が出始めた週末が専門医試験だったので、試験の日だけは吐き気止めを飲みましたが、それ以外は点滴も薬も必要なくやり過ごす事ができました。
日付:2011年4月10日 カテゴリー:妊娠中のトラブル~体験談版~
妊娠初期のトラブル~つわり~
妊娠すると様々な体の変化が起きてきますが、多くの方が最初に経験するのがつわりです。
吐き気・嘔吐以外によだれが多量に出るといった症状が出ることもあります。
吐き気が強くて食事が摂りにくくなったり、食べると吐いてしまうというケースが典型的ですが、中には空腹時の方が吐き気を強く感じてしまうため常に何か口にしていなければいけなくなる「食べつわり」の方もいらっしゃいます。
いずれも、早ければ妊娠5週くらいから症状が出始めて10週を過ぎると徐々に落ち着いてくる事が多いようです。中には16週を過ぎても気持ち悪さが続いたり、妊娠中はずっとスッキリしないままという事もあります。
つわりそのものは、妊娠によるホルモンの変化で起きてくるものなので、ひどくなければ治療の必要はありません。
食べられるものを食べたい時に欲しいだけ食べるというのが基本的な対処法になります。
空腹時に吐き気を感じる場合は、ポケットにビスケットや一口大のおにぎりなどを持っておいてこまめに口にすると楽に過ごせます。夜間寝ている時が一番空腹になりやすいので、枕元にもつまめるものを置いておくといいでしょう。
また、何度も吐いてしまうと脱水になりやすくなるのでこまめに水分は摂ることがポイントです。
飲料を飲むと吐いてしまう場合は、スポーツドリンクやフルーツジュースなどをシャーベット状にするか製氷皿で凍らせたものをあめのようになめると水分補給がしやすくなります。
受診が必要なのは次のようなケースです。
*何度も吐いて食べ物も飲み物も口にできない
*尿量が減って1日に4~5回しかトイレに行かない
*吐いたものに血液が混ざる
*体重が5キロ以上減り続けている
妊娠してすぐにつわりで体調が悪くなると、この先10ヶ月も自分の体はもつのだろうかと不安になるかも知れませんが、つわりは必ず落ち着いてきますから心配いりません。
不妊治療の第1ステップ・タイミング法
ひとくちに「不妊治療」と言っても、タイミング法や漢方治療から体外受精といった高度な生殖補助医療まで幅があります。年齢や不妊の原因によって、タイミング法から徐々にステップアップしてもいい場合もあれば、いきなり体外受精が必要な場合もあるんですね。
タイミング法というのは、排卵日の見当をつけて妊娠の可能性が高い時期を狙って夫婦生活を持つという方法です。精子の寿命が3~4日間くらいで卵子の寿命が約24時間なので、排卵日の3日前と排卵日当日にタイミングを合わせるのが一番効率がいいと言われています。
ただ、お仕事の都合などでなかなかこの通りに夫婦生活を持てないということもありますから、排卵4日前~排卵日のどこかでチャンスを作るつもりでいればいいでしょう。
排卵日を予測する方法は次のようなものがあります。
基礎体温をつける
排卵日チェッカーで調べる
超音波検査で卵胞の大きさを調べる
上から順に、下に行くほど確実な方法になります。
月経周期がある程度安定している方は、周期から14日を引いた日数が大体の排卵のタイミングになりますので、例えば30日周期の方でしたら月経初日を月経周期1日目として16日目辺りが排卵日ということになります。
周期にばらつきがあったり、基礎体温をつけてもよく分からないという方は、普段そろそろ排卵日かなと思っているタイミングで一度超音波検査を受けてみるといいでしょう。
超音波で卵巣を見れば、どのくらい排卵の準備が進んでいるかが確認できますので、よりピンポイントで排卵日を予測する事が可能です。
日付:2010年11月25日 カテゴリー:不妊症
子宮頸がんとHPV感染
子宮頸がんの検診で異常が出た方の中には、HPV検査を希望される方もいらっしゃいます。
検診の結果が「ASC-US」だった方は、HPVハイリスクタイプの検査が保険でできますが、それ以外の結果の方は自費での検査になります。
また、HPVのどのタイプに感染しているかを調べることで、今後持続感染するリスクや子宮頸がんに進んでいくリスクをある程度予想することができるので、タイピング検査を希望なさることもあります。
HPVタイピング検査は、約15種類あるHPVハイリスクタイプの感染の有無を調べる検査です。自費の検査になるので、12600円のご負担が必要になりますが、16型と18型に感染しているかどうかも確認できるため、今後ワクチンを打って明らかに効果が期待できない方を判別することが可能です。
子宮頸がん検診で異常が出ていても、治療が必要な段階までは進んでおらず、HPV16型か18型に感染さえしていなければワクチンを打つ意味はゼロではありません。
検診で異常が出てしまったからワクチン接種をどうしようか・・・と迷っていらっしゃる方は、まずタイピング検査を受けてみてはいかがでしょうか。
HPVは一度感染しても多くは持続感染せず自然に活動が抑えられていきます。HPVのタイプによって持続感染しやすいものと活動がおとなしくなりやすいものがありますが、ウイルスの活動が制御されればHPV検査は「陰性」になりますし、子宮頸がん検査の結果も正常化していくことが多いですね。
いったん感染したHPVを治療する薬はありませんので、自分自身の免疫力を高めて、持続感染・再感染を防ぐしかありません。
HPVは、性交渉の経験がある女性の8割が一生に1度は感染するといわれているくらい非常にありふれたウイルスです。10代や20代前半の感染率はほぼ50%というデータもあるくらいです。
性交渉の開始年齢をできるだけ遅くしたり、コンドームで予防を心がけることはとても大切ですが、100%予防する方法は感染前のワクチン接種以外にないのが現状です。
子宮頸がんの検査で異常が出てHPV感染が心配・・・という方は、お気軽にご相談下さいね。
日付:2010年11月1日 カテゴリー:性病,診療メニュー紹介
不妊が心配な時はまずご相談下さい
「不妊の相談」にいらっしゃる患者様には、すでに妊娠を目指してから2年以上たっている本当の「不妊症」の方と、まだ妊娠を目指し始めて間もないあるいはこれから妊娠を目指したいのだけど「何となく不妊症じゃないか心配」という方がいらっしゃいます。
どちらの場合も、まずは不妊症の基本的な検査を行ってその後の治療方針を決めていきます。
「不妊症」の定義に当てはまらなくても、より効率よく妊娠を目指したいと思ったら、早い段階で婦人科に行くのは選択の一つとしてありなんですよ。
もちろん、30歳以下でまだ年齢的にそれ程あせる必要がない方の場合、月経が順調で特に婦人科の病気をしたことがなければ、まずは基礎体温をつけながら1年くらい自然に任せても全然問題ありません。
人によっては、病院で検査を受けたり、排卵の時期のタイミング指導を受けたりすること自体がプレッシャーになってしまうという方もいらっしゃいますからね。
ただ、一度も婦人科検診を受けたことがない方や、月経不順の方は、妊娠したいなと思ったら一度はきちんと検査を受けておいた方が安心です。
また、35歳以上の方は、「自然」にこだわりすぎるあまり1年や2年を無駄に過ごしてしまうということはできれば避けた方がいいでしょう。
不妊の相談をしたからといってすぐにあれこれ治療をしなければいけないわけではありません。
検査で大きな異常がないかを確認し、タイミング法だけで様子を見れそうなのか、排卵誘発剤を使った方がいいのかなどの「見通し」を立てていくことが大事なんです。
いきなり検査をしたり、治療の選択をするのはちょっと・・・でも、不妊症について気になる、という方には「不妊カウンセリング」も行っています。
不妊カウンセリングは、不妊症の検査や治療にはどのようなものがあって、どういったタイミングで何を行っていったらいいのかをお話しする特殊外来です。
お話しのみの場合自費診療になりますが、まずは話だけ聞きたいという場合もお気軽にご相談くださいね。
日付:2010年10月19日 カテゴリー:不妊症,診療メニュー紹介
多のう胞性卵巣症候群とは
多のう胞性卵巣症候群(PCOS)とは、卵巣の中で卵の元=卵胞がうまく育たず、きちんと排卵しないために月経不順や不妊症の原因となる病気です。
次のすべての条件に当てはまった場合に、多のう胞性卵巣症候群と診断されます。
1)無月経・月経不順などの症状がある
2)血液検査(ホルモン値の検査)でLH/FSH > 1
3)超音波で卵巣の中に10個以上の卵胞が並んでいる(多のう胞性卵巣)所見がある
多のう胞性卵巣症候群の症状として、一番代表的なものが月経不順又は無月経ですが、これらの症状は排卵がうまくいきにくくなるために起きてくるものです。
排卵障害があるので、少量の出血がダラダラ続いたり、月経周期がもともと不規則であまり一定にならないという方が多く見受けられます。
それ以外にも、ホルモンの異常として男性ホルモンの増加やインスリン抵抗性が見られることがあります。
男性ホルモンが増えると、多毛やニキビなどの「男性化兆候」という症状が現れます。あごの周りなどにできやすい大人ニキビがなかなか治らなかったり、口の周りやお尻~太ももの産毛が濃くなったりします。
インスリン抵抗性というのは、血糖値をコントロールしているインスリンというホルモンが有効に働きにくくなることです。そのために、血糖値やコレステロールが高くなったり、太りやすくなったりすることがあります。
なので、多のう胞性卵巣症候群の症状の中には「肥満」が含まれています。
日付:2010年7月11日 カテゴリー:多のう胞性卵巣症候群,婦人科の病気