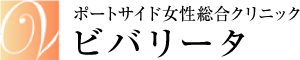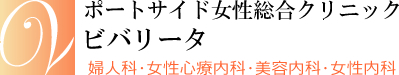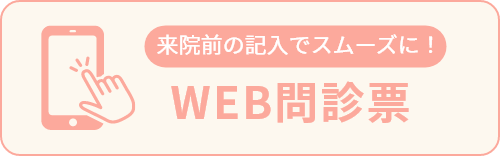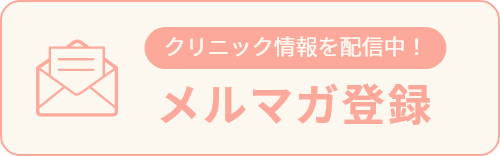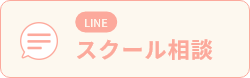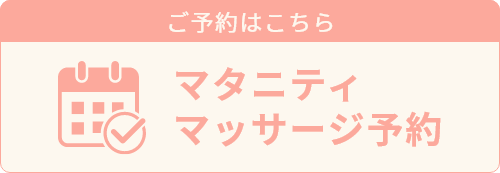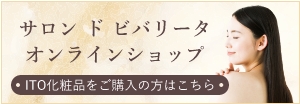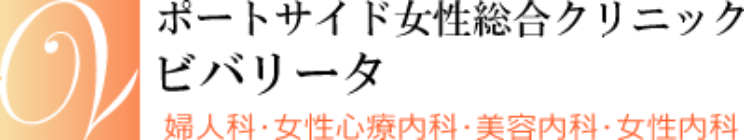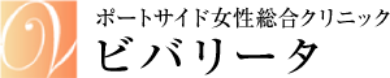婦人科の病気
おりものが増えたら性病?【横浜市の婦人科】
おりものが多い=性病なのなの?(横浜駅 おすすめ 近くの 婦人科)
おりものに変化があると、性行為の経験がある方の多くが「性病ではないか」と心配して受診なさいます。
特に、性行為後から症状が出たりすると余計に心配になってしまいますよね。
受診なさる方の訴えで多いのも、「おりものが増えた」「おりものの色がいつもと違う」「おりものの臭いが強くなった」「痒みが気になる」といったものです。
おりものに変化が起きる病気は
クラミジア性子宮頚管炎
淋菌性子宮頚管炎
トリコモナス腟炎
マイコプラズマ感染症
といった、いわゆる「性感染症=性病」と
細菌性腟炎=大腸菌や溶連菌などの雑菌による炎症
カンジダ腟炎=カンジダという真菌(カビ)による炎症
といった、性行為とは関係ないものがあります。
かゆみ=性病とも言えない(横浜市 評判いい 婦人科)
痒みが強いからと言って必ずしも「重症」であったり「性病」である可能性が高いわけではありません。
むしろおりものの量はそれほど多くはないけれどクラミジアに感染していたりするケースもあります。
また、強いかゆみとぽろぽろしたおりものが出たから「カンジダの症状」だと思っていたら、クラミジアも併発していたというケースもあります。
自覚症状だけで何の病気なのかを判断することは困難なのです。
「性病」かどうかは検査をすれば分かります(横浜駅 評判いい 近くの 婦人科)
いつもよりおりものが多いなと感じたり、臭いが強いかもと思ったら、早めに婦人科で検査を受けるようにしましょう。
主な検査は、おりものをぬぐい取って調べる「培養検査」や「抗原検査」です。
おりものはそれほど気にならないけれど、かゆみやしみる感じが強い場合、性器ヘルペスの可能性があるため、血液検査を行ったり、皮膚表面をこすって抗原を調べる検査を行う場合もあります。
性行為の経験がある方の場合は、「おりものや痒み」が出たら必ず「内診」は必要になります。
性行為の経験がなくても、カンジダ腟炎や細菌性腟炎になることはあります。この場合は、「内診」は行わず、外陰部の皮膚の状態を目で見て確認(視診)したり、表面に付着しているおりものを綿棒でぬぐい取って検査を行います。
性行為の経験がなければ、「内診」はしませんので安心して受診してくださいね。
「性病」の予防は定期検査とコンドーム(横浜市 おすすめ 婦人科 女医)
また、性行為の時に、「毎回」「正しく」「初めから終わりまで」コンドームが使用できているかどうかを改めて確認してることをお勧めします。
万が一どちらかが性感染症に感染していると分かったら、必ず2人そろって「治療」を受けるようにしましょう。たとえどちらかの検査が「陰性」でも、「偽陰性」の可能性がありますので、きちんと治療を受けた方が安心です。
おりものの色や臭いが気になる時は?性病の可能性は?
茶色や緑色のおりものは異常?(横浜 女医 おすすめ 婦人科 年末年始)
「おりものの異常」で受診なさる方は、気になってすぐに受診する方と、「結構前から気になっていた」という方に大別されます。
「いつもおりものが多い」「以前から痒みが続ている」「何となく臭いが気になっていたが様子を見ていた」という方も少なくありません。おりものの臭いや色がいつもと違うな~と思った時に、一番気になるのはそれが受診せず放置しても問題ないものなのかどうかでしょう。
おりものの異常のうち、カンジダやB群溶連菌・大腸菌といった細菌による膣炎であれば、自然に治ることもあります。一方、クラミジアなどによる性 感染症は自然に治ることはなく、パートナーも含めてきちんと治療する必要があります。
性 感染症、つまり性病に気付かずに放置してしまうと、パートナーとのピンポン感染やそれ以上の感染拡大のリスク、そして、感染がお腹の中に広がると「骨盤腹膜炎」という強い炎症が起きた状態を引き起こしてしまったり、将来的な不妊症のリスクにもなりえます。
おりものの異常は性病?(横浜駅 おすすめ 近く 婦人科)
少なくとも半年以内に性 行為があり、おりものの量が増えた・臭いが強くなった・色がいつもと違う・ピンク色や茶色いおりものが出る・血液がおりものに混ざるなどの症状がある場合は、様子を見ずに受診したほうがよいでしょう。
厳密には、おりものの状態だけでそれが「性感染症(性病)」かどうかを判断することはできません。おりものをぬぐい取る検査をして、そこにばい菌がいるかどうかを確認しなければ断定はできないのです。
おりものでわかる性感染症は、クラミジア頸管炎・淋菌感染症・トリコモナス膣炎・マイコプラズマ子宮頚管炎です。これらはいずれも性 行為によって感染するものですが、トリコモナスの場合はまれにプールや温泉などでの感染もあるので「絶対に性行為のパートナーから感染したもの」とは言えません。
ただ、多くの場合は性 行為が感染経路になるので、これらの菌が検出された場合はパートナーと一緒に完治が確認できるまで適切な治療を行う必要があります。
治療の途中で性 行為を行ってしまうと、治療が長引いてしまうので注意が必要です。
性交渉していなくても細菌性腟炎になる?(横浜市 評判いい 婦人科 女医)
一方、性行為は関係なく発生してくるおりものの異常は、主にカンジダ膣炎と細菌性膣炎によるものです。
カンジダ膣炎外陰炎は「カンジダ」という真菌(カビ)が繁殖して膣内や外陰部の皮膚に炎症を引き起こすものです。ぽそぽそした塊状のおりものや白~緑がかったおりものが増えて、膣内や外陰部に痒みを引き起こします。
細菌性膣炎は、大腸菌やB群溶連菌などの雑菌が増えて膣内に炎症を引き起こすものです。黄色っぽいドロッとしたおりものが増えたり、生臭い臭いが強くなることがあります。細菌性膣炎でかゆみが出ることはまれです。
大腸菌やB群溶連菌は自然に治る?(横浜駅 評判いい 婦人科)
カンジダ膣炎や細菌性膣炎は、自分の抵抗力がしっかりしていれば膣の「自浄作用」によってばい菌を洗い流すことができるため、2~3日で自然によくなることもあります。
数日おりものが気になっていたけれどすぐに改善したという場合で、性 行為の機会がなければそのまま様子を見てもよいでしょう。
ただし、性行為の機会がある場合は、一度は一通りの検査を受けておいた方が安心です。クラミジアも淋菌も、ほとんど症状が出ない人の方が多いため、隠れた感染が持続する場合があります。本当は、何も気になる症状がなくても、少なくともパートナーが変わったら感染症の検査を定期的に受けた方が確実なのです。
少しでも気になる症状があれば、自分で何とかしようとせず婦人科で相談しましょう。
ご予約はこちらから
生理不順はどこまでほっといてもよい?【横浜駅近くの婦人科】
どこからが生理不順?(横浜市 おすすめ 婦人科)
当院に受診なさる方の多くは、生理不順・生理痛・月経前症候群・不正出血など、何らかの「月経関連の症状」が気になって来院なさいます。
中でも比較的多いのは「生理不順」ですが、一口に生理不順といっても、「生理の周期が正常より長い」という場合もあれば「少量の出血が何度も来る」という場合もあれば「出血期間が長い」という場合もあります。
たまに、生理は定期的に来ていて、間で不正出血しているケースでも「生理不順」だと思って受診なさる場合もあります。
ちょっと生理が乱れただけで「生理不順」なのか、「どこからが生理不順なの?」と悩むケースもあるかもしれません。
正常な生理は、
*周期(生理が始まってから次の生理が来るまでの日数)が25~38日
*出血期間が3~7日
*生理と生理の間に出血しない
*排卵がある(基礎体温が2相性)
のすべてを満たしている場合です。
これらの条件のどれかに当てはまらなければ、何らかの異常が起きている「可能性がある」ということになります。
ただ、絶対にこの範囲に入っていないと「治療が必要」とは限りません。
ほっといてもいい生理不順もある?(横浜駅 評判いい 土曜日 婦人科)
例えば、生理の周期が40日くらいで少し長めだけれど、毎回排卵していて途中の不正出血もなく、生理の期間も5~7日でスッキリ終わる、というケースでは治療は不要なことがほとんどです。
生理の周期は、多少前後することがありますし、毎月ピッタリ同じ日や同じ周期で来なければ「異常」というわけではありません。
また、年齢的に40代後半にさしかかってから、徐々に生理の周期が短くなった、または長くなったという場合も、「年齢相応」の生理不順が起きている可能性が高いと言えます。
出血期間が長引いたり、不正出血が途中で起きたりしなければ、ほっといても大ごとにはなりません。
逆に、生理の周期はだいたい30日だけど出血量が少なくて基礎体温をつけてみると排卵していない、というケースでは年齢によっては治療が必要になる場合もあります。
よく、「生理不順はどこまでほっといて大丈夫ですか?」という質問を受けるのですが、医学的に「ほっておいてよい不調」はありません。
何らかの理由があってその不調が出ていることがほとんどなので、病院に行く必要はなくても、生活リズムや食事内容を見直したり、「見て見ぬふりをしてきた解決した方がよいこと」が隠れていないかをチェックした方がよいでしょう。
症状が出る直前に原因があることが多いのですが、中には「積もり積もった、見て見ぬふりをしてきた思い」や「以前から『何とかしなきゃ』と思いながらも蓋をしてきた課題」が原因になっていることもあります。
ほっといてはダメな生理不順(女医のみ おすすめ 土曜日 婦人科)
「受診が必要」もしくは「治療が必要」な生理不順はどのようなものかというと、大きく分けると3パターンあります。
*生理が来ない期間が長い(目安は60日・90日以上だと必ず受診)
*出血期間が長い(月のうち半分以上出血していたら受診)
*不正出血と区別がつかない(生理不順だと思っていたらがんだったということがないように)
他にも、「妊娠を希望している」という場合は、少しでも気になる症状があれば早めに受診して検査だけでも受けた方が安心です。
できるだけ婦人科は受診せずに何とか済ませたい、と思ってしまう方は多いかもしれません。
でも、体がせっかく「生理不順」という分かりやすい症状で何かを知らせてきてくれているわけです。これを機会に、自分の体と向き合ったり、日々の過ごし方を見直してみてはいかがでしょうか?
ご予約はこちらから
かゆみやおりものは性病?
外陰部のかゆみが「性病」とは限らない?(横浜駅 おすすめ 近くの 婦人科)
外陰部の痒みは、カンジダ腟炎などの雑菌による炎症が原因となる事もあれば、ナプキンかぶれやかみそり負けなど物理的な刺激によるものが原因となる事もあります。
もちろん、ヘルペスなどの性感染症によって皮膚の症状が出ていることもありますが、どちらかというと雑菌が原因となっているケースの方が多くなります。
最近は、VIOの脱毛を受ける方も増えてきているので、脱毛前の自己処理や光脱毛後の乾燥などで痒みを引き起こしてしまうケースもあるようですね。
外陰部に症状が出ると、「性病なのではないか?」という不安を抱える方もいらっしゃいます。
痒みと一緒に、おりものの異常もでたりすると、いろいろ心配になるかもしれません。
実際は、痒みを引き起こす原因として多いのは、カンジダ腟炎や接触性皮膚炎なので、「性病」であるケースはどちらかというと少ないのですが。
時々、痒みが気になるということで検査を行うと、クラミジアやヘルペスが陽性で出る場合もあります。
自覚症状が出にくい性感染症(性病)もあるので、症状の有無や、どのような症状があるかだけで、性感染症の可能性について判断することはできません。
外陰部の痒みに市販薬を使ってもよい?(横浜市 評判いい 女医だけ 婦人科)
外陰部の痒みに対して使用できる市販薬があります。
これらは、ドラッグストアで自分で購入できるものです。
「デリケートゾーン用」と書いてある軟膏は、多くの場合、かゆみを抑える成分がメインの軟膏です。塗ると少しスースーする感じが出るものもあるので、塗った時に刺激が強いと感じたり、逆にしみてしまう場合は使用を控えましょう。
また、明らかにカンジダによる痒みだとわかる場合は、カンジダ腟炎やカンジダ皮膚炎に対する腟剤や軟膏も市販されています。薬局薬剤師さんに相談して、選んでもらってもよいでしょう。
市販薬の中にも「ステロイド」が含まれているものもあります。ナプキンかぶれなどで、炎症がひどくなっている場合は、ステロイドが含まれたものを使用することもありますが、外陰部にステロイドを長期に使用することはあまりお勧めできません。
いずれの市販薬を使用する場合も、3~4日で症状が改善しなかったり、塗ったら悪化してしまう場合は、すぐに婦人科を受診しましょう。
受診が必要なおりものの異常は?(横浜駅 評判いい 近くの 婦人科)
もちろん、以下のような症状があれば、直ちに受診することをお勧めします。
・痒み
・おりものが多い
・おりものが臭う
・おりものに血液が混ざる
・おりものの色がいつもと異なる
・外陰部がひりひりする
・外陰部にできものができている
たとえこれらの症状がなくても、コンドームを使わずに性行為を行う機会があったり、パートナーが変わったりした時には、定期検査として性感染症の検査を受けておくと安心です。
検査をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
また、セルフチェック(自己検診)キットで陽性が出た場合の治療も承っております。
検査結果がわかるものをご持参いただきましたら、当院で同じ検査を行うのではなく、まず治療を行ってから、治療後の再検査のみを行います。セルフチェック後の治療も保険診療で対応できますので、安心して受診なさってください。
◆◆◆当院はGME医学検査研究所の提携医療機関です◆◆◆
生理痛をコントロールしておいた方がいい理由は?【横浜駅近くの婦人科】
ひどい生理痛は「内膜症予備軍」?(横浜市 おすすめ 婦人科 土曜日)
一昔前は、「生理痛は病気ではない」という考え方もあったようですが、最近では「鎮痛剤が必要なレベルの生理痛は内膜症予備軍」という考え方に変わってきています。
つまり、日常生活に支障が出たり、鎮痛剤を飲まなければやり過ごせないほどの生理痛が出るということは、「すでに内膜症という病気が始まりかかっているかもしれない」と考えた方がよいということです。
どの程度の痛みが「治療が必要なレベル」の痛みなのかは、厳密な意味で定義することはできません。痛みの感じ方は個人差が大きく、また検査をして客観的に数値化することもできないため、「このレベルだと治療が必要ですよ」という明確な基準は作れないのです。
受診が必要な生理痛とは?(横浜市 評判いい 婦人科 土曜日も)
生理の時に、多少下腹部が痛くなったり腰がおもだるくなるけれど、鎮痛剤を飲まなくても普段通りに動けるし、スポーツや趣味も楽しめるというレベルであれば、医学的には問題ないと言えるでしょう。
逆に、次のような状態の場合は、我慢せずに早めに婦人科を受診することをお勧めします。
*生理の時期には必ず痛み止めが必要
*生理の時期に学校や仕事を休んだり早退することがある
*生理を理由に日常生活や社会活動をセーブすることがある
*年々生理痛がひどくなっている
*年々生理の量が増えている
*生理の時期に腹痛以外に頭痛・吐き気・下痢などの不調がでる
生理痛の検査は?(横浜駅 おすすめ 近くの 婦人科)
生理痛について診察を受ける場合、できれば受けた方がいいのが「超音波検査」です。性行為の経験がある人は、膣から超音波の機械を入れて(非常に細い機械です)「経腟超音波検査」を行います。性行為の経験がない人は、肛門から機械を入れる「経直腸超音波検査」か、お腹の上から機械を当てる「経腹超音波検査」を行います。
「経直腸超音波検査」の方が、子宮や卵巣の状態を詳細に観察することができますが、下着をとって検査を受ける必要があります。検査に抵抗がある場合は、まず「経腹超音波検査」を受けて、より詳細に観察した方がいい場合はMRI検査を追加するという方法もあります。
どの方法で検査を行うかは医師の判断によりますが、受診前に不安が強い場合は事前に電話で問い合わせて希望を伝えておくのも一つの方法です。
生理痛の治療はピルや黄体ホルモン療法(横浜市 評判いい 婦人科 土曜日)
生理痛の治療の中心は、ピルや黄体ホルモン剤によるホルモン治療です。漢方や鎮痛剤で痛みを和らげることもできますが、これらの対症療法だと内膜症を予防することはできません。
生理痛がひどくなりすぎないうちにコントロールしておく最大のメリットは、将来的な内膜症のリスクを減らせるという点です。
そのほかにも、ピルや黄体ホルモン療法で生理痛や生理の量をコントロールすることによる多くのメリットがあります。
*学業や仕事のパフォーマンスが保たれる
*「生理にうんざり」することがなくなり「自分が女性である」ことを受け入れやすくなる
*ナプキンやタンポンの使用量が減る
*将来的な不妊リスクが減る
*貧血や鉄欠乏を改善できる
もちろん、薬を飲めば副作用のリスクも発生します。上記のメリットと、副作用によるデメリットと、どちらが自分にとって大事なのかをしっかり考えてみることをお勧めします。
関連記事:「生理痛の重さレベル診断!対処法や受診すべき目安も解説」エミシアクリニック
生理痛と月経困難症【横浜ベイクウォーター近くの婦人科】
「生理痛」は婦人科の「病気」?(横浜 評判いい 近くの 土曜日 婦人科 女医)
生理の時に多少下腹が痛くなったり腰が重くなったりするのは、子宮の周りに血液が滞るせいなので、特に「異常」というほどのことではありません。むしろ、生理の時も全く無痛という人の方が珍しいでしょう。
生理の初日や2日目に下腹の痛みがあるけれど痛み止めを飲むほどではないし、学校や仕事にも特に支障はないという人は、日ごろから体を冷やさないようにしたり、定期的な運動の習慣をキープすれば大丈夫。定期検診を受けて、子宮や卵巣に異常がないことを確認していれば、病気の心配をする必要もありません。
生理痛が問題になるのは、痛みが非常に強くて日常生活に支障が出たり、毎回痛み止めを何錠も飲まなければいけなかったりするケースです。生理のたびに寝込んで仕事を休むような人は、「単なる生理痛」と放置していてはいけません。
特に、以前は効いていた痛み止めが効かなくなってきたり、痛み止めが効いている時間が短くなってきていたりしたら要注意です。この場合、生理痛の原因となる病気が進んできている可能性もありますから、早めに婦人科を受診する必要があります。
生理痛がひどい時に行う検査は、「超音波検査」です。内膜症が疑われる場合は、血液検査で腫瘍マーカーを調べたり、生理の量が多い「過多月経」も伴っている場合は貧血の有無を調べたりすることもあります。超音波検査は、生理中でもできますが、異常なほどの出血があるなどの緊急性が高い場合を除いては、生理中ではない時に検査を受けた方がよいでしょう。
婦人科的検査に抵抗があるかもしれませんが、性行為の経験がない人は、お腹の上から超音波検査を行うこともできます。
生理痛で冷や汗が出て倒れたり、救急車を呼ぶほどの痛みが出る場合は、すぐに婦人科を受診しましょう。生理痛だけではなく、頭痛や吐き気が一緒に出て寝込んでしまったり、痛みのせいで意識が飛んでしまうような場合も、直ちに受診が必要です。
例え今は何も異常がなくても、放置すると将来の子宮内膜症リスクになりえます。
ひどい生理痛は月経困難症(横浜市 おすすめ 年始 婦人科)
寝込むほどの生理痛は、「月経困難症」という病気になります。月経困難症は、痛み止めがなければ我慢できないほどの生理痛が一番特徴的な症状です。中には痛みがひどすぎて立ちくらみを起こしてしまったり、吐き気を伴ったりする人もいます。
時々、「腹痛を起こした若い女性が駅で倒れました」と救急隊から連絡が入ることがあるんですが、救急車で運ばれてきた方を診察してみると実は生理痛がひどすぎて倒れただけだった、ということも少なくありません。救急車を呼ぶほどの生理痛でなくても、痛みのせいで学校や仕事を休まなければならない場合は、「病気」のレベルと言えます。
月経困難症は、ひどい下腹部痛以外にも、頭痛・めまい・腰痛・下痢などの様々な症状が出ることがあります。なぜこんな症状が出るのかというと、痛みを伝える「プロスタグランジン」という物質が子宮のお部屋の中の「子宮内膜」からたくさん放出されてしまうからなんです。プロスタグランジンは、痛みを伝えるだけではなく、腸を動かしたり血管の壁を収縮させたりする働きを持っています。生理の時期に子宮内膜が分厚くなると、このプロスタグランジンが出すぎて様々な症状を引き起こすことになります。
異常がなくてもひどい生理痛は治療が必要(横浜駅 評判いい 年始 近くの 婦人科)
診断は、基本的に「自覚症状の強さ」で判断します。つまり、客観的に月経困難症かどうかを診断する「検査」はなくて、本人がどれだけその痛みやその他の症状で困っているかが判断基準になるというわけです。
血液検査などのように数値で表すものがないだけに、どの段階で受診や治療が必要なのか自分では判断がつかないかもしれません。
受診のタイミングの目安としては、毎回痛み止めが必要なほどの痛みがある・生理痛で寝込むことがある・痛み止めを飲んでもあまり効かない・生理痛以外にも症状がある・痛みが年々ひどくなっている、などの場合、婦人科で検査や治療を受けた方がいいでしょう。
もちろん、そこまで痛みはひどくないけれどもっと快適に月経期間を過ごせるようにしたい、という場合も婦人科で相談することをお勧めします。
救急車で搬送されるほどの生理痛だったとしても、検査をすると何も異常が見つからないこともあります。ひどい生理痛の原因として多いのは、子宮内膜症や子宮腺筋症ですが、これらの病気が超音波検査やMRIで見えるサイズになっていない場合、「検査では異常がないけれどひどい痛み」が出ることはあります。もちろん、検査をしてこれらの病気が見つかった場合は、放置せず適切な治療を受けましょう。
生理痛は我慢するものではありません。改善する方法があるのに、何もせず毎月月経のたびに憂鬱な気分で過ごすのは「あなたらしさ」をちょっと取りこぼしているかもしれません。適切な治療や生活改善で、快適な毎日を手に入れることが可能です。
月経困難症の治療はピルか対症療法(横浜市 評判いい 年始 婦人科)
救急車で運ばれるほどの生理痛であれば、例え画像上何も異常がなくても治療が必要です。
また、そこまでひどい生理痛ではなくても、痛みのせいで何らかのパフォーマンスに影響が出ている場合は、「薬による治療」も視野に入れた方がいいでしょう。
生理痛の治療は、大きく分けると
*ピルや黄体ホルモン剤によるホルモン治療
*痛み止めや漢方による対症療法
があります。
ホルモン療法に抵抗があるという場合や、痛みがひどい月とそうでもない月があるという場合は、まずは、漢方薬で体を温めて、痛い時だけ痛み止めを飲むといった対処をしてみてもいいでしょう。
痛み止めが効かない場合や、過多月経も伴っている場合は、ホルモン療法を選択した方がよいと言えます。特に、生理の量が多くて貧血になっている場合は、放置してはいけません。
ピルは、卵胞ホルモンと黄体ホルモンが混ざった合剤です。卵胞ホルモンが入っているので、吐き気や頭痛などの副作用が出る場合があります。ただ、こういった副作用で「ピルが飲めない」という人はごく稀です。ほとんどの方は、「飲み初めにちょっと気持ち悪かったけれどすぐに慣れた」とおっしゃいます。
副作用がなければ、ピルは、生理痛を軽くしてくれるだけではなく、生理前の不調を改善したり、生理が来る日を自由にコントロールできるというメリットがあるので、女性の生活の質を非常に改善してくれます。
たまに、「ピルを飲んだら余計に生理痛がひどくなった」という方がいらっしゃいます。ピルの種類によって、痛みや出血量がどのくらい軽くなるかの差があります。
1つの種類で十分な効果が得られなかった場合、別の種類に変えたり、連続服用することで症状が改善する場合もありますので、医師に相談してみるといいでしょう。
何らかの血栓リスクがある場合や、吐き気でピルが飲めない場合は、黄体ホルモン剤が適しています。
ピルと同様に排卵を抑えて生理の量を減らすため、血栓症のリスクは上げずに生理を軽くしたい人にお勧めです。
どの治療が適しているのかは、生理痛のひどさや、個々の生活スタイルにもよりますので、一度婦人科で相談してみてください。
ご予約はこちらから
女性が貧血になる原因
貧血は女性に多いのはなぜ?(横浜 婦人科 おすすめ 女医 土曜日)
男性に比べて女性の方がもともと血液が薄く、貧血かどうかの基準である「血色素(ヘモグロビン)」の正常範囲が男女で異なります。
その基準値に当てはめても女性の方が「貧血」と診断されることが多いのは、何といっても「月経」があるからです。
毎月定期的に血液を失っているわけですから、月経量が少しでも多かったり、月経周期が短かったりすると簡単に貧血になってしまいます。
もちろん、食事からとる鉄分の量が少なかったり、運動や発汗で鉄分を失うということもありますが、月経の影響が圧倒的に大きくなります。
逆に言えば、思春期前(初経前)や閉経後の女性が貧血になっていたら、それは何か重大な病気が隠れている可能性を考えなければいけません。
健診で貧血を指摘されて当院を受診なさったけれど、婦人科疾患が何もなかった方でほかの病気が見つかったケースは
*再生不良性貧血(血液の病気)
*胃潰瘍
*大腸の炎症性疾患
*膀胱がん
などです。
もちろん、子宮筋腫や子宮腺筋症などの明らかな婦人科的病気がなくても、生理の量が多くなることもあります。
「生理の量が多い」は放置してはダメ!(横浜駅 評判いい 近くの 婦人科)
貧血の原因の多くは「過多月経」です。生理の量が多くて、生理のたびに少しずつ貧血になっていっている場合、かなり貧血が進行しないと自覚症状が出ないことがあります。
「なんだかフラフラする」「最近階段がスムーズに上がれない」とおっしゃって受診なさった方の中には、貧血の指標である「ヘモグロビン(血色素)」が6未満であった方もいらっしゃいます。(正常値の半分以下)
このくらい重度の貧血になると、心臓に負担がかかりすぎて急に倒れたり、場合によっては心臓の動きに支障が出ることもあります。
月経量が多いかどうかを判断する一つの目安は「一番多い日に普通の日用ナプキンが2時間もつか」です。
もし、昼間でも夜用ナプキンが必要だったり、普通のナプキンでは2時間もたない場合は出血量をコントロールしておいた方がいいでしょう。
よく、「レーバー状の塊が出るかどうか」をチェックしましょう、と書いてあったりしますが、塊が出てきても、トータル量としてナプキンが3~4時間持つ量であれば、月経量は正常範囲の可能性があります。
健診で貧血を指摘される、または貧血の項目が「ギリギリ正常」だったのが異常値に入ってきた、という場合はすぐに婦人科を受診した方がいいでしょう。
生理の量が増える原因は?(横浜市 おすすめ 婦人科 女医 土曜日)
生理の量が多くなる原因として多いのは、子宮筋腫や子宮腺筋症、そして子宮内膜増殖症です。稀に、双角子宮などの子宮の形そのものの先天的な異常が影響していることもあります。
また、これらの「子宮の形」に異常をきたす病気がなくても、ホルモンのアンバランスや体質的な個人差の範囲で、月経量が増えることもあります。
10代の月経が安定しない時期や、逆に閉経間際の排卵が起きにくくなってくる時期も、ホルモンの影響で生理の量が急に多くなることもあります。
健診のたびに貧血を指摘されたり、ナプキンから漏れてしまうことが多いなと感じている人は、これらの病気がないか一度は婦人科で検査を受けることをお勧めします。
◆◆貧血改善のための食事については以下の記事が参考になります◆◆
【医師監修】貧血に良い食べ物一覧|鉄分量で比較するおすすめ食材と献立例を紹介
◆◆関連記事◆◆
「その下腹部の痛み、放っておいて大丈夫?—見逃せないサインと対処法」
東京新宿区の胃カメラ・大腸内視鏡検査・肛門科のRENA CLINIC(レナクリニック)
ASC-US(アスカス)で「がん」の診断になることはある?【横浜駅近くで評判の婦人科】
「ASC-US(アスカス)」はどういう意味?(横浜 おすすめ 婦人科 女医 土曜日)
会社の健診などでうけた子宮頚がん検診の結果で「ASC-US」だった場合、通常は「早めに婦人科を受診しましょう」と書かれています。その後の検査はどうすればよいのか、急いで受診した方がいいのか、気になりますよね。
「ASC-US」は「アスカス」と読みます。
日本産科婦人科学会のガイドラインでは、細胞診(子宮頸がんの検診で行う検査)で「ASC-US」だった場合は
1)すぐに精密検査(コルポスコピー検査+組織診)
2)HPV検査を追加
3)6か月後に再度細胞診検査
のいずれかを行うことになっています。
当院では、まずHPV検査を行って、「陽性」だった方のみ精密検査を行っています。HPVが陰性であれば、1年後に細胞診を再検査すればよいからです。
HPV検査というのは、HPVの中で子宮頸がんの原因となりうる「ハイリスクタイプ」に感染していないかどうかを調べる検査です。
HPVには100種類以上の「型」があり、そのうち約15種類の「型」が子宮頸がんの原因となります。代表的なのは、16型や18型ですが、31型や52型でも子宮頸がんになることがあります。
HPVが陽性だと危険?(横浜市 評判いい 婦人科 土曜日)
細胞診がASC-USで、HPVが陽性だった場合、それが直ちに「がんである」という意味ではありません。
HPVがどのくらい悪さをしているのか、細胞の変化がどの程度かを確認するために、精密検査として「組織診」を行います。少しまとまった細胞をかじりとる検査で、多少の痛みと出血を伴います。
この組織診の結果によって、その後の流れが決まっています。
軽度異形成(CIN1)だった場合→4~6カ月ごとに細胞診を行う
中等度異形成(CIN2)だった場合→3か月ごとに細胞診を行うか治療に進む
高度異形成(CIN3)またはそれ以上だった場合→治療に進む
「ASC-US」で「がん」になることは?(横浜駅 近く おすすめ 婦人科 女医 土曜日)
検診で「ASC-US」を指摘された時点で、「これは『がんですよ』という意味なのだろうか」という心配が出てきがちですが、精密検査の結果で返ってくるのはほとんどが軽度異形成~中等度異形成です。
ただ、まれに、細胞診が「ASC-US」だったけれど精密検査では「上皮内癌」だったというケースもあります。
なので、「ASC-US」は「軽い変化の可能性が高いけれど『放置してよい』という意味ではない」と理解していただくのがよいかと思われます。
検診で何らかの異常を指摘された場合は、ご自身の心身の状態と向かい合う「チャンス」です。そのままにせずに早めに婦人科を受診して適切な検査や治療を受けるようにしましょう。
ご予約はこちらから
日付:2026年1月31日 カテゴリー:HPVワクチン,子宮頚がん
ピルの連続服用と周期投与はどちらがよい?【横浜の婦人科】
ピルを休薬しない連続服用とは?(横浜駅 おすすめ 近くの 婦人科)
月経困難症つまり生理痛の治療薬として発売されているピルには「低用量」と「超低用量」があり「超低用量」のピルには「周期投与」と「連続投与」という2種類の服用方法が選択できるタイプがあります。
ピルは婦人科以外でも処方してもらえますが、「どの種類がいいのか?」「どういう飲み方がいいのか?」なども相談したい場合は、産婦人科でピルを処方してもらった方がいいかもしれません。
「周期投与」は、「周期的に月経様出血(消退出血と言います)を起こす」方法で服用するという意味です。21日間実薬を服用し、7日間休薬するか、24日間実薬を服用し4日間偽薬を飲むことによって、28日サイクルで定期的に消退出血を「来させ」ます。
一方、「連続投与」は、実薬を服用する期間を引き延ばすことによって消退出血の間隔を28日よりも延長して「年間の出血回数を減らす」方法です。
具体的には、実薬を77日間服用して7日間休薬するタイプと、実薬を最長120日まで連続服用して4日間休薬するタイプがあります。簡単に言うと、毎月休薬せず、3~4か月に1回休薬することで、消退出血の回数を年間3~4回に減らすことができるということです。
連続投与のメリットは?(横浜市 婦人科 評判いい 女医 土曜日)
毎月ピルを休薬する「周期投与」のメリットは、「生理が毎月来る」ことで安心感を覚える方にとっては「周期が整う」というメリットがあります。また、毎月出血を確認することで「妊娠していないことの確認」をしている人にとっても、周期的に出血があることが安心につながるでしょう。
しかし、医学的には毎月出血を「わざわざ来させる」メリットはなく、むしろ、トータルの出血量が増えたり、毎月痛みを感じることによるデメリットの方が大きくなる可能性があります。
実際、内膜症のリスクはトータルの出血量と比例して高くなるというデータもありますので、毎月出血を来させるより年間3~4回の出血で済ませた方が内膜症リスクも減らすことができるのです。
ピルを休薬せずに次のシートを飲む「連続投与」のメリットは、出血回数を減らすことによって、月経前後の不調を感じる回数を減らし、貧血も予防でき、内膜症リスクも下げることができるという点が挙げられます。
ピルを飲んでいても、PMSの症状が休薬前から休薬中に出てしまうという場合も、休薬の回数を減らすことによって、不調が出る期間を減らすことが可能です。
休薬しないデメリットは?(横浜市 おすすめ 婦人科 女医 土曜日)
休薬せずに飲み続けるデメリットとしては、連続服用している途中で不正出血が起きてしまうことがあるという点です。長期間服用し続けることによって、途中の不正出血は起きにくくなりますが、患者様のお話からの印象ですと、飲み初めの3~6カ月間は「3シート連続しようと思ったけれど途中で出血してしまった」といったことが起こりうるようです。
どのくらいまで飲み続けると出血が起きるのか、自分のリズムがつかめてくると、思わぬ出血が起きる前に休薬をとったりしてうまくコントロールしていけます。
よく、「出血が来ない間は子宮の中に『不要なもの』がたまっていくのですか?」ということを質問されますが、ピルの働きとして出血の元となる「内膜」を「厚くさせない」という効果があります。なので、飲み続けている間も子宮の中に内膜が「たまらない」ようにしているのです。
毎月子宮から出血させないと、余分な血液がたまったり、体の中に「デトックスできない」ものがたまる、という心配は全くありません。そもそも、生理の時に出てくる血液は、子宮内に作られた「内膜」であって、体内にたまった「毒素」ではありませんので、月1回の出血で「デトックス」しているわけではないのです。
実際、28日周期で出血を来させていた時よりも連続服用した時の方が出血量が減ってきたという方の方が多いので、「3カ月出血を止めていたら3か月分たまりにたまった分がどっと出るのではないか」という心配は不要です。
当院では、すべての種類のピルを処方しています。
ピルの種類も徐々に増えてきていますから、ぜひご自身のライフスタイルに合ったピルをチョイスしてみてくださいね。
ご予約はこちらから
日付:2026年1月31日 カテゴリー:生理痛
腟カンジダの薬を入れると白いカスが出る?【横浜駅近く女医のみの婦人科】
「腟カンジダ」は性交渉していなくてもなる?(横浜市 おすすめ 婦人科 女医)
「腟カンジダ」は性行為とは関係なく発生する、おりものの異常や痒みを伴う膣や外陰部の炎症性疾患の一つです。白っぽい塊状のおりものが増えるのが特徴的で、「外陰部腟カンジダ症」や「カンジダ腟炎」と呼ばれることもあります。
「カンジダ」という真菌(カビ)の一種が腟内で増殖することによって引き起こされるもので、性行為の経験がない若い方でも発症することがあります。
カンジダそのものは皮膚の表面などに付着している比較的ありふれた弱い雑菌で、通常は膣内に紛れ込んでも「自浄作用」によって洗い流されます。
タンポンやナプキンを長時間取り替えられなかったり、冷えや寝不足などによって自浄作用(本人の免疫力)が落ちたり、抗生物質を服用したりすることで、通常は増えないはずのカンジダが腟内で増えすぎると「腟カンジダ」になることがあります。
また、よく「抗生物質を飲んだらカンジダになる」と言われているのは、膣内を守っている善玉菌が抗生物質でいなくなってしまうからです。
腟内には、酸を産生して膣の中を守ってくれている善玉菌がいます。この菌のおかげで、カンジダ=真菌(カビ)は増えにくくなっているのです。
抗生物質を飲むと、良い菌も悪い菌もいっぺんに抑えられてしまうため、一時的に腟内が無防備な状態になってしまいます。その時に、膣内にカンジダがいると、兵隊がいなくなった隙に暴れてしまう、という現象が起きやすくなります。
「腟カンジダ」の症状は?(横浜駅 評判いい 近くの 婦人科 土曜日)
「腟カンジダ」の主な症状は、白いポロポロしたおりものと腟内や外陰部のかゆみです。炎症がひどくなると、外陰部がヒリヒリしたり腫れぼったい感じが出ることもあります。
おりものの状態は、よく「カッテージチーズ」「酒粕」「消しゴムのかす」といった表現で説明されますが、普段のおりものよりも塊になっているものが増えて、ひどいと黄色や黄緑色に見える場合もあります。
軽いと、上澄み液が混ざったヨーグルトのような感じになることもあります。明らかな塊のようなおりものになっていなくても、おりものが増えて少し酸っぱいにおいが強くなった時などは、カンジダが悪さをしていることもあります。
痒みは、膣のふちや、ひだ(小陰唇)の内側がかゆくなることが多いですが、範囲が広がると、尿の出口周囲や肛門周囲まで痒みの範囲が広がることもあります。
腟内が痒くなることもしばしばあり、少し腫れた感じやあつぼったい感じに感じられるのが特徴です。実際は外陰部は腫れていないのに、「腫れたように感じる」痒みが出るのが特徴です。
痒みや炎症がひどくなると、石鹼や尿がしみる場合もあります。また、かゆくて無意識にひっかいてしまうと、皮膚を掻き壊してしまい、ひりひりする原因になることがあります。
痒みが強い時は、氷水につけたガーゼやタオルを外陰部にあてて冷やすと、痒みが落ち着きやすくなります。できるだけひっかかず、鎮静するようにしましょう。
「腟カンジダ」の検査は何をされる?(横浜 おすすめ 婦人科 女医)
おりものが増えたり、痒みが気になるといった症状で婦人科を受診した場合、まずはおりものの中の菌を調べる検査を行うのが一般的です。
内診が可能な方の場合は、クスコという内診用の器具を使って腟内の状態やおりものを観察し、おりものをぬぐい取って検査を行います。病院によってはその場で結果が出ることもありますが、たいていは1週間程度で検査結果が分かります。
内診ができない方の場合は、クスコは使わず、表面に付着したおりものをぬぐい取って検査を行います。外陰部を綿棒で少しこするだけなので、痛みは伴いませんが、下着を取って検査を受ける必要があります。
また、外陰部の皮膚の状態を目で見て、ある程度炎症が強いかどうか、ヘルペスやコンジローマの可能性がないかを確認します。
「腟カンジダ」の治療で腟剤を入れると白いカスが出る?(横浜駅 おすすめ 婦人科 女医)
「腟カンジダ」の治療は、カンジダを抑える薬を腟内に入れるか内服します。性行為の経験がない方は、内服薬の方が使いやすいので、症状や年齢に応じて腟剤と内服薬を使い分けます。
外陰部の皮膚にも炎症が広がっている場合は、塗り薬も併用することもあります。
婦人科で検査をした時に、明らかに「腟カンジダ」が疑われる場合は、その場で腟内を消毒してカンジダを抑える腟剤を入れることもあります。
この「膣内に入れる薬=腟剤」は、座薬のようにタブレット状になっていて、膣の中で徐々に溶けるつくりになっています。入れた直後から表面がとけ始めますが、通常は数日かけてゆっくりとけます。
なので、腟剤を入れた後2~3日経ってから、溶けだした腟剤がおりもののように流れ出てきたり、ぽろぽろしたカスが出てくることがあります。診察の2~3日後に白いカスや塊状のものが出てきたら、それはお薬の破片である可能性が高いのでそのままにしておきましょう。
カンジダの薬を入れた後、白いカスのように出てくるのは、腟剤を入れた直後というよりは数日後からのことが多く、たいていは2~3日でなくなります。「カンジダの治りかけにおりものが増えた」「白いカスはいつまで続くの?」といったご相談もありますが、痒みが落ち着いていれば1週間程度で徐々に改善することが多いので数日間は様子を見ても大丈夫です。
たまに、お薬が合わずに、溶けだしてきたものでひりひりしてしまう方がいらっしゃいます。外陰部に薬の破片が付着してしみる場合は、軽くシャワーで外陰部を洗い流すとよいでしょう。
また、薬を入れたのに痒みが続く場合は、腟剤が溶け出したせいというよりも、ほかの原因で炎症が起きている可能性もあるので、再度診察を受けた方が安心です。
治療してもらったはずなのに、急におりものが増えたように感じられるとビックリするかもしれませんが、腟剤を入れた後であればお薬が溶け出してきているだけなので大丈夫です。
もし、腟剤を入れてもらってすぐ翌日に全部出てきてしまったりした場合は、治療が不十分になる場合もあります。カンジダの薬を入れたのに痒みやおりものが続いていたら、再度受診することをお勧めします。
ご予約はこちらから(横浜市の婦人科)
◆◆◆当院はGME医学検査研究所の提携医療機関です◆◆◆
日付:2026年1月31日 カテゴリー:おりものの異常,婦人科の病気